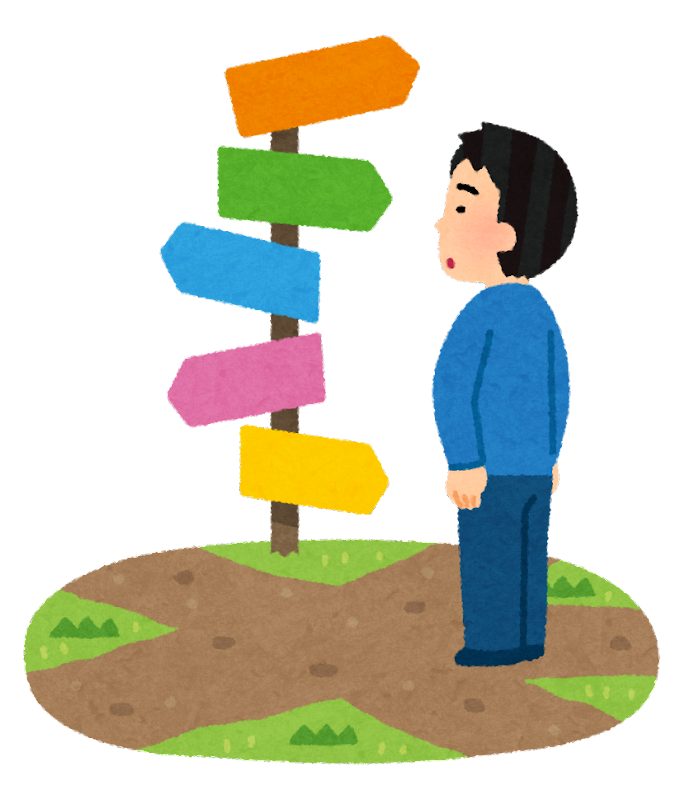今日の心がけ~職員のスピーチ~
どうしてそうなるの?
2021.08.27
情報が飛び交う現代社会では、必要な情報や知識の収集に注力してしまい、情報を吟味し、その意味を考えて自分のものにするという「熟成」のためのプロセスが疎かになりがちです。
東京大学大学院教授の柳川範之氏は「こういう時代だからこそ、相対的に大事になってくるのは、得られた情報や知識を自分の中でどう加工するかをじっくり考え熟成させることです」
と著書で述べています。
例えば本を読むときには、書いてあることをただ鵜呑みにせず、絶えず自問自答しながら読むことにより、自分で理解してきたものが、もう一段階熟成されていくきっかけになります。
物事を様々な情報と絡めながら、自分の中で考えていくことは、現実社会に役立つ独創力や発想力を養うもとになるというわけです。
その時その場において、〈どうしてそうなるのだろう?〉と立ち止まってみることは、新しい発想につながる思考実験といえるかもしれません。
今日の心がけ◆常に本質は何かを考えましょう(「職場の教養」一般社団法人 倫理研究所より)
パソコンやスマートフォンが普及している現在では、知識や情報を手に入れることは一見たやすいことのように感じます。
知りたいと思ったその場で情報に触れることができ、本当に便利な世の中になったと感じることも多いです。
しかし、ネットから得た情報が本当に正しいのか、自分が得たかった情報なのかを吟味する必要があります。
先日、隣町の手芸店まで買い物に行く際、開店しているのかスマートフォンで調べました。
ネット情報では開いているとのことだったので行ってみると、お店は閉まっていました。
少し考えてみれば、お盆休みの期間、小さな個人商店という条件のもとでは、お休みしているほうが自然です。
調べた情報源も地図アプリのもので、お店のホームページではなかったということも失敗の要因でした。
簡単に得られるネット情報を鵜呑みにして、思考を巡らせなかったことを反省しました。
学生にもこのような傾向はみられ、図書館で調べものをしている際、上手く本から情報を得られないと、「本をじっくり読むのは面倒」「ネットで探すからいいです」と簡単に諦めてしまう人もいます。
本を読むことは時間がかかり、遠回りしているような気がしますが、1冊読めば、著者が調べ考え抜いた知識や見識を得られるため、実は、物事の本質をとらえる近道であると考えます。
さらに、考えるだけでは、記憶から消えていってしまうことが多いので、読んで得た知識をもとに考たことメモし、文章化していくことも大切です。
書いてまとめる作業をすることで考えが深まり、記憶に定着しやすくなります。
読む・考える・書くというサイクルを習慣化して物事の本質をとらえられるよう努めたいです。
学生にも折に触れて、伝えていきたいと思います。
図書館 大木