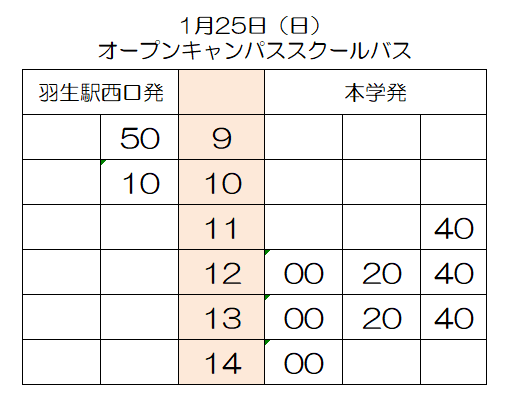今日の心がけ~職員のスピーチ~
「外国人と接する機会」
2024.03.04
日本政府観光局の統計によると、2018年に日本を訪れた外国人旅行者数は三千万人以上を記録しました。
この二十年間で七倍以上となり、業務や日常生活においても、様々な国の人たちと接する機会が増えることが予測されます。
例えば、近年イスラム圏からの観光客の増加を受け、「ハラール認証」を取得する飲食店が増えています。
「ハラール」とは、イスラムの教えにのっとって処理された食べ物を指し、認証を取得した店では教えに沿った食事が提供されます。
その他、礼拝に対応するため、駅、空港、デパートなどに「祈禱室」を設ける動きも広がっているようです。
街中で外国人と接する際に、文化や習慣の違いを感じることがあるかもしれません。
まずは、その違いを知ることが大切です。
日本人にとって馴染みの薄い文化や習慣であっても、その起源や詳細を知り、理解することで親近感へと変わり、誤解をなくすことに繋がるはずです。
文化の違いを知り、自国文化を再認識する契機にしたいものです。
今日の心がけ♦文化や習慣の違いを知りましょう
当たり前と思っている習慣も、世界に目を向ければ日本と全然違うことがたくさんあります。
日本ではトイレやお風呂など使用後は、扉を閉めます。
でも海外では扉が閉まっていると誰かが使用中と思ってしまうので使用後は使用後は扉を開けたままにするようです。
私たちが海外に行くときにネットの情報だけでは得られないリアルな喜びや伝わらない悔しさといった貴重な経験ができます。
日本では当たり前のことが海外では全く違うといった面白さを知る事ができると思います。
食堂 竹島
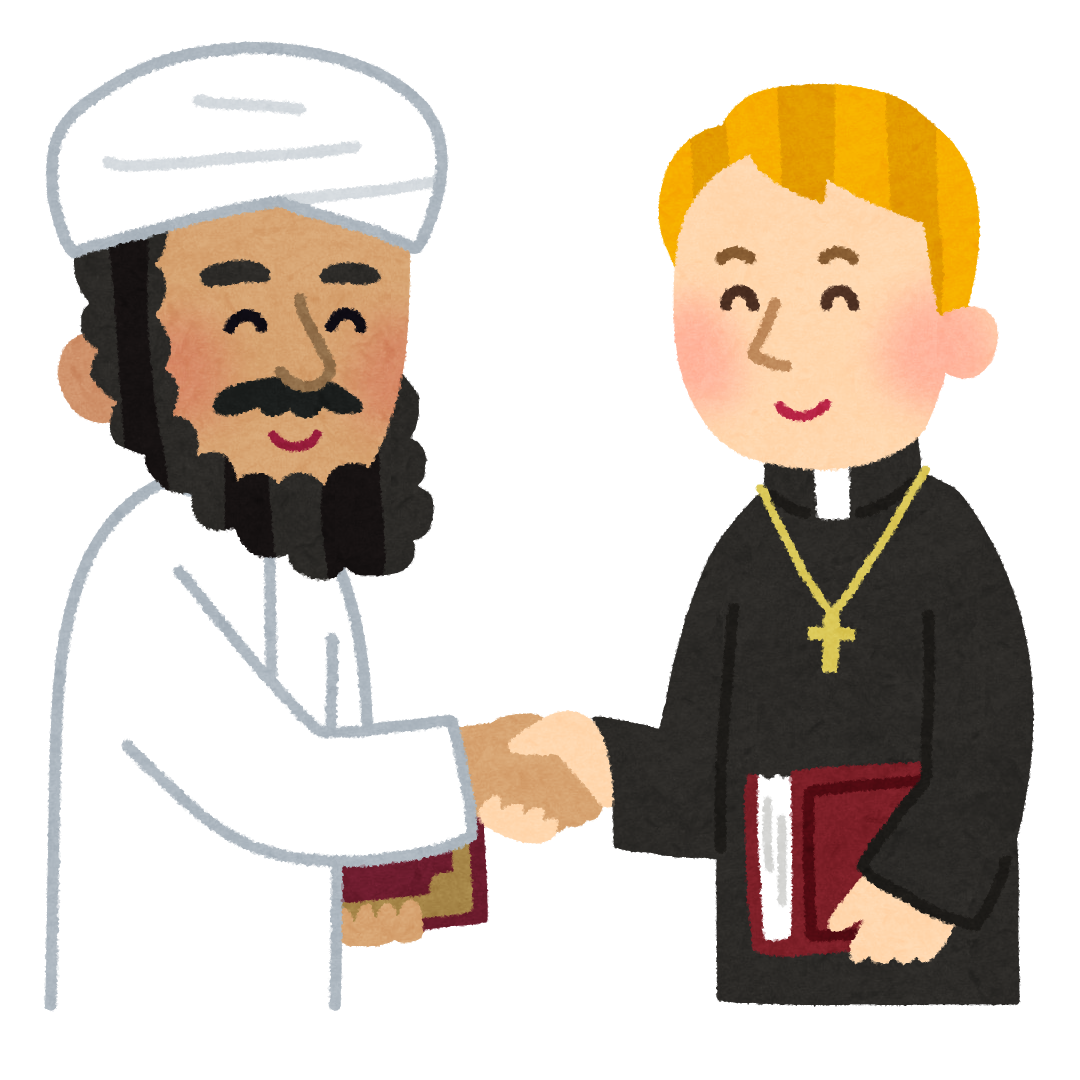
そうですね。
異文化と接するときには十分に注意しなければならないことが今もまだ多いですね。
本学も今後増えていくと思われる異文化の人々と抵抗なく接していくために「異文化理解」の科目をおいています。
その一環として、インドネシアのガネシャ国立大学やサラスワティ外国語大学との連携をして交流を行っています。
同じアジアと言っても国ごと、地域ごとに文化が異なっています。
例えばインドネシアと言っても島や地域により、文化様式は様々で、宗教でも、バリ島ではヒンズー教、その他ではイスラム教などと異なります。
現在、羽生市でも総人口は減少傾向を示していますが、外国人人口は上昇しています。
この傾向は羽生市に限らず全国的なものとなっています。
グローバル化が進む現代、コスモポリタン的な考えや行動が求められています。
異文化と付き合うためには、自国の文化に誇りを持ちながらも、相手の文化を容認するだけの度量が必要です。
このようなことから少しずつ文化的交流が生まれ、新しい文化が育っていきます。
いずれはこのことが拡がり、多文化がアタリマエとして捉えられる日が来るでしょうね。
藤田