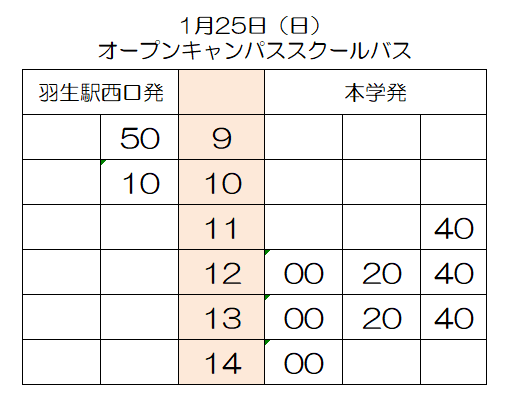今日の心がけ~職員のスピーチ~
快適な職場形成
2022.12.20
M者は、働き方の改善に取り組んでいます。
様々な意見が飛び交うものの、「一人ひとりの能力を最大限に発揮するのに何が必要か」という議論から、なかなか先に進みません。
意見の中には、体力や健康維持に努めること、専門技術を磨くこと、資格を取得することなどが出ていました。
そのために何をしたら良いのかという具体策について、熱心に話し合いました。
会議も最終段階に入った頃、リーダーが「こうやって議題を解決するために、皆で悩み、答えを出そうとするプロセスは、とても良い経験だ」と言いました。
そして、問題や課題を解決する力を持つことが大切であること、お互いに意見をぶつけ合う行為が重要であることを共有できたのです。
M社の社員は、個々人の能力開発前に、コミュニケーション力や、話しやすい職場作りを推進することの必要性を学んだのでした。
現在、そのきっかけとして、職場で明るい挨拶が交わされています。
今日の心がけ◆挨拶に磨きをかけましょう(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
能力を最大限に発揮するのは、家庭でも職場でもコミュニケーションが取れているかということが、とても大切だと感じています。
職場の場合、普段からコミュニケーションが取れていれば、誰かがミスをしても、みんなでサポートし問題解決すぐに行うことができます。
また、お互いの癖や、やり方を知っていれば、苦手な部分をフォローし合ったり、得意なことは任せたりと、効率良く仕事を進めることもできます。
このように、お互いが助け合うことで、信頼関係が生まれ、無駄もなくなり会社全体の利益にも繋がるのではないかと思います。
そのためにも、まずは挨拶をきっかけにコミュニケーションをとっていければ良いなと改めて思いました。
学生係 田口
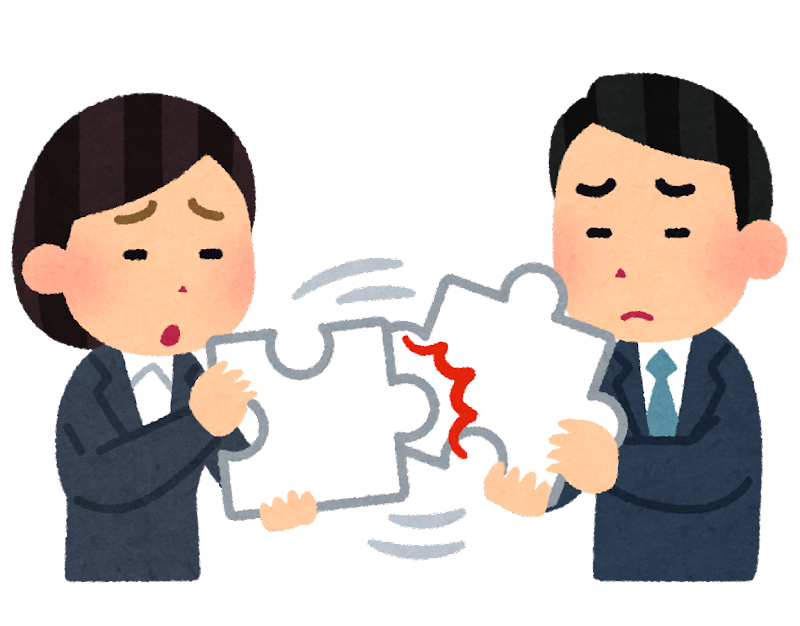
そのとおりですね。
本学でも教職員の間の「報・連・相」を確実に、円滑なコミュニケーションの第一歩の挨拶を、などを共有しています。
物事を考え、実行するためには一人の力は限られています。
いろいろと異なった考えを持った人々が一つの目的に向かって行動することによって多くのことが成し遂げられます。
「協力」の「協」の字源をみると「力をあわせる」で、「力」が3個、この「三」は多いという意味の他、いろいろな不思議な意味を持ちます。
このように「三人寄れば文殊の知恵」ではありませんが、多くの異なった個性が多く集まる多様性のある組織は発展します。
しかしそこに参加する人には基本的に「課題を解決しよう」とする強い意志を持った者であることが前提です。
その中で、多くの意見が交わされることが解決へ導きます。
そのためにも日ごろからの円滑なコミュニケーションが図られる環境が重要ですね。
本学の学生が目指す保育者は、連携がなければなりません。
そのためにも本学に在籍している間にこの良好なコミュニケーションがとれるようにしたいですね。
まずは教職員からその手本を示していきましょう。
藤田