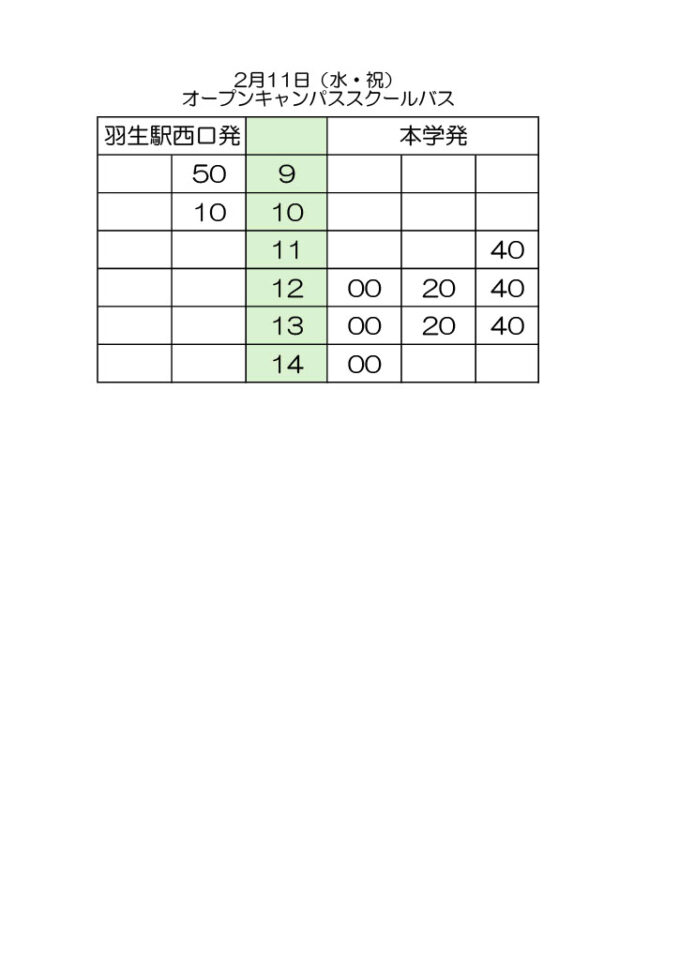今日の心がけ~職員のスピーチ~
待つということ
2022.11.02
私たちは、いつも何かに「待たされて」います。待ち合わせの相手、メールの返事、注文した品などの日常的なもの、採用通知、病気の診断結果など人生を左右するものまで様々です。
待っていない時間のほうが少ないかもしれません。
精神科医の春日武彦さんは、
「待つという行為は、それが切実なほど、待ち時間が長いほど、こちらの心が弱っている時ほど、妄想的な色彩を帯びがちとなります。考えが現実離れしていったり、被害妄想的になっていきかねない」と、著書の中で書いています。
待っている時の心の持ち方で、その時間を長く感じたり、短く感じるのはよくあることです。
急いでいる時は、たった数分の電車の遅れに苛立ったり、運の悪さを嘆いたりしてしまいます。
待つことに心を囚われることなく、憂えることなく、その時その場を懸命に生きたいものです。
待つ時間を有効に活用することができれば、「待たされている」ことから、少しでも解放されるのではないでしょうか。
今日の心がけ◆待つことを楽しみましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
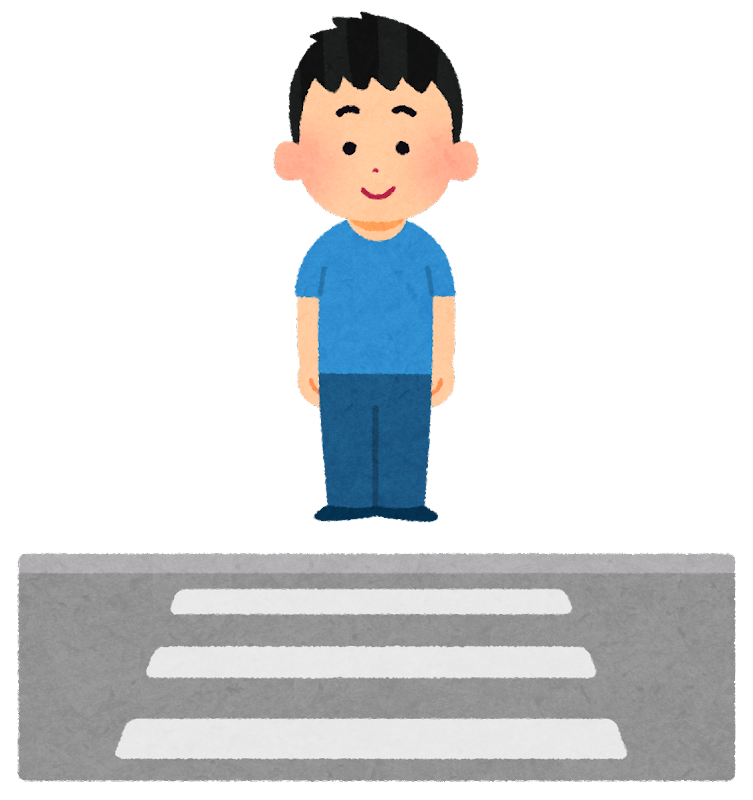
現代人は待つ時間というのが少ないと思います。
また、コロナ禍になり、オンラインでの会議や打ち合わせが当たり前になった世の中で、先方へ伺わなくても打ち合わせができるなど、タイトスケジュールで予定を組んでもより効率的に仕事をすることができます。
さらに、スマートフォンによる普及で「待つ」という行為は、昔に比べて減少しているように思います。
それでも、やはり待つことは起こります。
入場制限しているお店は一定数の客が入った場合は外で待ったり、アトラクションを並ぶ際も待つ時間が生まれます。
どうしてもスケジュールに空き時間ができそうだなというときは、本や動画をダウルロードしておくなど、有効活用できそうだなと思う場面に対応します。
また藤田先生が、いつもポジティブに考えるという思考法を私も見習いながら、待つ時間は考えごとをしたり、頭の中の整理するチャンスの時だと考えるようにしたいと思います。
荒井文菜
そうですね。
「待つ」を「待たされている」と感じている状態では、この「待つ」は消極的、受動的で苦痛を伴うものとなります。
これを積極的、能動的に「待つ」、さらに「待ってあげている」と考えれば、なんでもないことから優位な気持ちにもなることができます。
ビジネスでは「待った方が優位」と言われます。
積極的に待つためには「これから起きることを積極的に想定する」ことが大切です。
待つことに苛立つことより、待つことに楽しさと喜びを感じることです。
待たせている人には「焦り」とともにマイナスの感情でいっぱいになっているでしょう。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。」で始まる「方丈記」を読みながら、ゆったりとした気持ちで待ちましょう。
しかし、現代社会はスピードを求められていますから、自らは「待たせない」を念頭に入れた行動をしましょう。
特に「返事は待たせることなく必ず早めに」です。
「返事がないのは無視、無関心」と思われるとともに、子どもからの信頼を失うこともあるでしょう。
子どもを相手にする本学の学生には「子どもを待たせない」「子どもに我慢させない」を心掛けてもらいたいものです。
そのためにも、我々が学生を「待たせない」ようにしていきましょうね。
藤田