今日の心がけ~職員のスピーチ~
息子との会話
2022.11.02
単身赴任で家族と会話をする機会が少ないA氏は、帰宅した際には、極力家族と会話をするよう心がけていました。
家に帰ると、妻は留守中の出来事を中心に話を始めます。
息子の学校生活の様子も話してくれます。
しかし、中学一年生の息子は、思春期のせいか、自分からあまり話そうとはしません。
ある時、A氏は、息子が中間テストの期間中に家に帰りました。勉強をしている息子に「頑張っているな」と声をかけましたが、返事がありません。
普段なら「返事ぐらいしなさい」と??るところですが、その日はそっとしておきました。
テスト最終日の朝、息子が妻に「行ってきます」と言った声を聞いて、A氏も見送ろうと玄関に向かいました。
すると、息子が「父さん、頑張ってきます」と言ってきたのです。
日頃、息子の態度に一喜一憂し過ぎていたことを気づかされたA氏。
父として夫として、離れていても大きな心で家族を見守っていこうと決めたのです。
◆今日の心がけ◆家族をおおらかに見守りましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
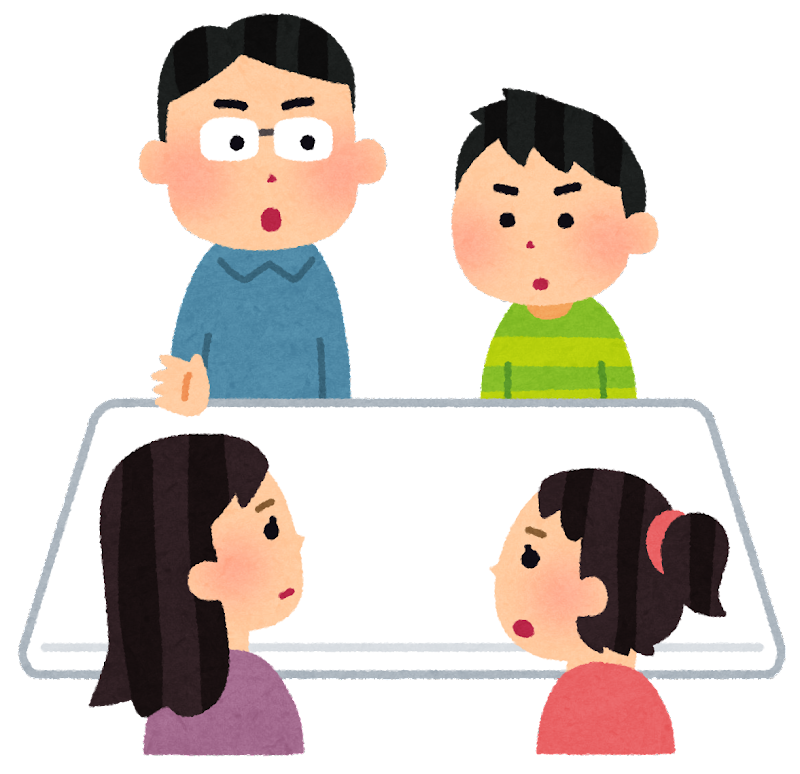
私も父が単身赴任をしていた時に、中学生だった経験があり、このお話が自分のことのように感じながら読みました。
単身赴任中の父が帰ってくるのは、安心することだったり、嬉しいことだったりする反面、どう接したら良いのか分からない気持ちでいたことを思い出しました。
多分、他の家族も同じような感じだったのではないかと思います。
このお話しの息子さんと同じように、話しかけられた時は、試験の最中で自分のことで気持ちがいっぱいいっぱいだったり、素直に返事をすることが照れくさい年頃だったりして、すぐに言葉を返せず、悪いことしたなと、ずっとどこかにひっかかっていても、どうしたら良いのか分からず、結局そのままになってしまったことがほとんどです。
ですが、このお話しの息子さんは、後にはなってしまいましたが、お父さんが自分の状況を察して、必要以上に声をかけずに待ってくれていることをに気付き、ちゃんと自分から返事を返すことができました。
このように、相手に自分の望む状況を要求する気持ちではなく、お互いがそれぞれの状況や気遣いを察することができる、おおらかな気持ちであれば、守る立場の大人も、守られる立場の子供も、家が心地よい空間になると思います。
子供の頃の私は、親の気遣いを察することが出来ませんでしたが、今は、親の立場にはなれなくても、察することはできるようになりましたので、親子間だけではなく、周囲の人に対しても、なかなか難しいことではありますが、出来るだけおおらかで、待つことができる人でいられるように心がけたいと思いました。
庶務係 大澤
そうですね。
子どもが思春期に入るとこのようなことが起こり始めますね。
自我の確立の時期だからかもしれませんね。
特に最も身近な親に対して相談することはいろいろな感情から難しくなります。
決して親を嫌っているからそうなるというわけではありませんね。
それこそ、本人にもその理由が分からない状態です。
人間の感情と行動の不一致ほど不思議なものはありませんね。
何故だかわかなないうちに感情とは異なった行動に出てしまう場合も良くあります。
特に近しいほど、気になる存在であるほど、このようなことが起こります。
これには時間が一番の薬となり解決してくれます。
お互いがお互いを思いやることから生じる不思議な感情ですからね。
成長の過程でほぼすべての人がこのような経験をしますから。
藤田

















