今日の心がけ~職員のスピーチ~
雪晒し
2022.10.07
江戸時代後期の越後縮の商人・鈴木牧之は、初めて江戸へ上った時に、江戸の人々が越後の雪の多さを知らないことに驚きました。
そこで、雪国の生活を紹介しようと『北越雪譜』を執筆・出版しました。
江戸市中で圧倒的な人気を溥したこの風物誌は、現在では、雪国独特の習俗や伝承などを記録した、民俗学上の貴重な資料として評価されています。
牧之は『北越雪譜』の中で、越後縮の雪晒しについて次のように述べています。
「雪の中で糸を作り、雪の中で織り、雪水にそそいで雪の上に晒す。
雪があって縮がある。……魚沼の雪は縮の親と言ってもよい」
雪晒しとは、織り上げた布を雪原の上に広げてお日様に晒すことで、越後縮を作る上で、なくてはならない工程です。
雪晒しは、まさに雪深い越後の風土を活かした暮らしの知恵といえます。
『北越雪譜』には、雪国・越後で生まれ育った鈴木牧之の郷土愛が込められているのです。
今日の心がけ◆先人の知恵に学びましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
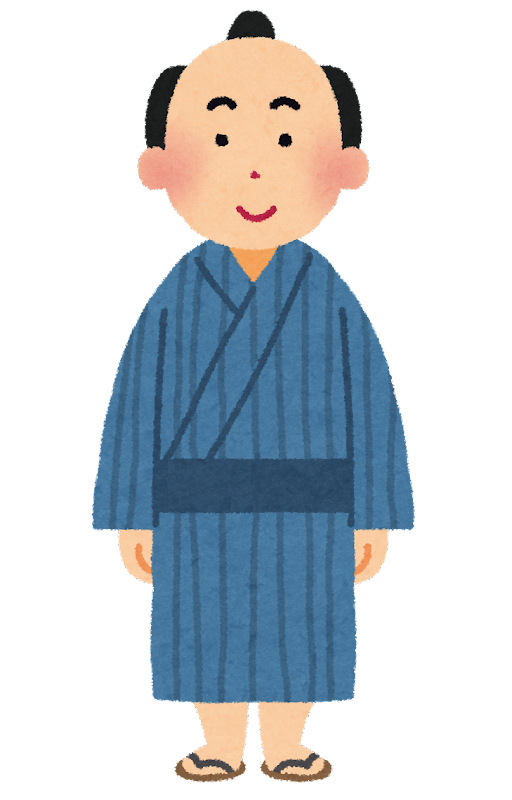
雪晒しという工程や言葉を知りませんでしたので、少し調べてみました。
雪が紫外線を反射することを利用して、晴れた日に雪上に麻織物や竹細工などを並べて漂白することを雪晒しといい、強い紫外線が、溶けた雪から立ち上る水蒸気に当たると、化学反応でオゾンが発生し、オゾンの植物繊維を漂白する働きを利用したものだそうです。
雪晒しにより白地の白が冴え、染料の色が鮮やかになり、2月下旬から4月上旬頃の晴れた日に行われる雪晒しは、雪国越後の風物詩ともなっているとのことです。
今日の心がけの「先人の知恵に学びましょう」とありますが、先人は年配の人や、高齢者に限らず、その経験をした人、その体験をした人、その体験から知識を得ている人だと思います。
そういった人たちの話を聞いたり、本を読んだり、またはインターネットやブログなどで、その経験や体験を知ることができます。
自分にとって知らない知識を、先人の経験や体験をとおして知っておくことで、こんな場合はこうしよう、こういうときはそんな方法もあるのか、などたくさんの知恵を自分につけることができます。
自分が興味のあること、自分が不安に思っていること、そういったことほど、先人たちの貴重な経験や体験から学んで、行動していく知識にしていきたいと思います。
実習指導係 林
そうですね。
鈴木牧之の『北越雪譜』の現代語訳を25年位前に友人からもらったことがあります。もう一度読み返さなくては・・・。
人は周りのことに目を向けるのに忙しくて、この情報化社会の現代でも少し離れた外のコトの多くを知りません。
ましては¥やこの頃は交通網すら十分でない時代ですからね。
最近、NHKの番組「知恵泉」をはじめとしてテレビで「先人に学ぶ」番組が増えてきたような気がしています。
自分が興味あるから多いような気がしているのかもしれませんが・・・。
現代は核家族化などで衣食住の全てにおいて変化し、人間の生活力がや機能が衰えてきているように感じています。
各家庭で代々行われてきた伝統的行事も、生活の知恵 おふくろの味などの継承が少なくなっているように感じています。
伝統的に守られてきた知恵には、それぞれ地域や家庭の実状に合わせたいろいろな工夫があります。
世界中のいたるところで暮らしを支えてきたこのような「知恵」「工夫」の多くは、現代の科学でもその効用が証明されているようです。
なにげなく、おじいちゃんやおばあちゃんから教わったことが理にかなっており、現代でも十分に通用することを改めて感じることも多いですね。
本学では”Think Globally, Act Locally.”(地球規模で考え、地域からでも行動を)のために「ふるさと学」や「異文化理解」を科目においています。
地域の伝統文化を学び、世界の文化を学び、多様性を理解したうえで保育現場で活かすことができればとの考えからです。
人はその地、その気候など自然環境とともに工夫し、知恵として蓄えてきています。
保育者を目指す本学の学生には、このことを理解し、先人を敬い、先人から学ぶ謙虚な姿勢で保育に臨んでもらいたいと考えています。
藤田

















