今日の心がけ~職員のスピーチ~
「おつかれさま撲滅運動」
2022.10.05
2009年にカルビーの代表取締役会長兼CEОに就任した松本晃氏が、入社早々に取り組んだのが「おつかれさま撲滅運動」でした。
「『おつかれさま』。これが日本の挨拶なのか!朝から疲れていたら仕事にならない。朝の挨拶は『おはようございます』、午後にあったら『こんにちは』だ」と述べる松本氏。
以後「おつかれさま」「おつかれ!」の使用を禁止しました。
「おつかれさま」とは本来、相手の労苦をねぎらう意で用いる言葉ですが、職場で同僚と顔を合わせた時や、メールの文面に何気なく使うことが多いでしょう。
氏の取り組みは、職場で当たり前になっている習慣を見直す大切さを示唆しています。
挨拶だけでなく、職場で当たり前になっている習慣を見直してみましょう。
その中で〈おかしい〉と感じていることがあれば、改善策を提案しましょう。
初めは違和感のあった習慣も、毎日の業務の中では、いつの間にか当たり前のようになってしまうものです。
改善や新しい取り組みを始めることで、職場が活性化し、それが新たな発想のヒントに繋がります。
今日の心がけ♦当たり前の習慣を見直しましょう
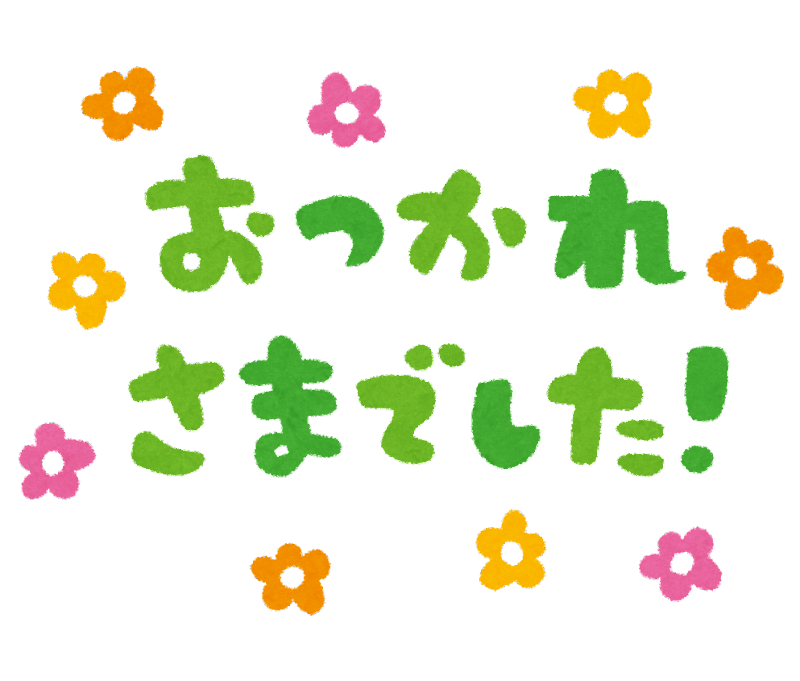
私はこれを読んで、当たり前について考えてみました。
当たり前のことなどないという事に気が付きました。
当たり前と思うと、ありがとう、ごめんなさいという気持ちが無くなってしまいます。
食事が出来てあたり前
電車が時刻通りに来てあたり前
こんな日常に対して感謝の気持ちを持ちたいと気づかされました。
食堂 水村
そうですね。
こちらからのアタリマエは相手側のアタリマエとはかりぎませんからね。
何気なく口から出てきてしまう「お疲れさま」や「ご苦労様。」
この言葉は年齢や性別によって受け取り方や使い方も異なると調査結果もあります。
どちらも相手を思いやる(ねぎらう)言葉です。
黙っているより良いかもしれませんが、人によっては「疲れてない」と言う人もいるかもしれません。
言葉は時代とともに変化してきますから、善し悪しは難しいところです。
ただ、重要なことは「相手を思う心」です。
「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」「また明日」など挨拶も同じですね。
何も言わないよりは言った方が相手との心の距離を縮めることは間違いありません。
同じ使うならば、できる限りポジティブと言われる表現を一言添えることが良いでしょうね。
何でもアタリマエのことと思うことなく、相手を思う心で接していきましょうね。
特に「信頼される保育者」を目指す本学の学生がこのことを実践できるように教職員から率先して使いましょう。
藤田

















