今日の心がけ~職員のスピーチ~
畳のふち
2022.08.29
和室を歩く時、「畳の縁や敷居を踏まないように」と教えられたことはありませんか。
なぜ踏んではいけないのか理由を紹介しましょう。
畳の縁は、その家の格式を示し、家紋を入れることがあります。
これを踏むことは、ご先祖さまや家人の顔を踏むことにつながり、失礼なことになります。
また、敷居を踏むと磨り減り、畳の縁も踏めば傷んでしまいます。
家を大切にする気持ちの表れとして、敷居や縁を踏まないようにと言われます。
こうした由来には、諸説ありますが、踏んではいけない理由を知ると、自然と敷居や縁を避けることができるでしょう。
幼い頃、祖父母から聞いたような、迷信のように思える事柄にも、相手を思いやる気持ちや物への心遣いが息づいているものです。
今日の心がけ◇マナーの由来を知りましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
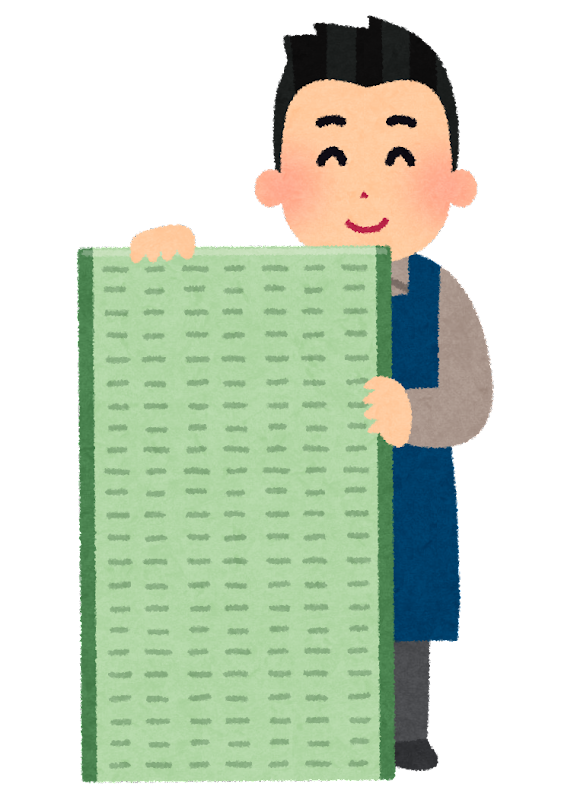
三世代同居の家庭で暮らしていた私にとって祖父母から学ぶ事も多く、そのひとつに六曜があります。
これは大安、仏滅など日にちの吉凶を占う指標とされているものです。
七五三などのおめでたい行事は良い日と言われる日程を選び、
お祝いやお見舞いを届ける際には必ずカレンダーを確認していたことを記憶しています。
こちら側が気にしていなくても、相手の方やそのご両親の気に触ることもあるので気をつけるようにと言われた事を覚えています。
その時の祖母の言葉に深い意味はなかったと思います。
しかし相手を敬い相手の立場で物事を考えられるようにとの教えなのだと私自身で勝手に解釈しています。
最近は自己中心的で身勝手な事件が多くそのようなニュースを聞く度に心が痛みます。
人間関係が希薄になり他者との距離が広がる一方ですが、こんな時だからこそ本学の学生には子ども達との関わりを大切にし、思いやりの心を繋いで行って欲しいと思いました。
教務係 寺田
そうですね。
「しきたり」は文化ですからね。
昔からその組織や集団で規範として行動様式で、これを守ることによりその集団が問題を起こさず活動できたのでしょう。
マナーその集団が争いごともなくも穏やかに暮らしていくための暗黙の了解でしょうね。
エチケットはこれを維持するためにお互いが相手を不快にさせないための申し合わせのようなものでしょうか。
それが生まれ、定着するまでにはいろいろな経緯があったでしょう。
そして、集団内の皆にいきわたるには時間がかかったことだと思います。
また、時代とともに少しずつ変化していることも確かです。
これらはともに「相手やモノなどを大切に扱う」ことが共通していています。
しかし、その集団によってこれらが異なることも確かです。
そのために相手の文化を理解すること、自文化を相手にきちんと理解してもらえるよう説明できることが重要となります。
本学ではこのため「ふるさと学」や「異文化理解」といった科目をおいています。
保育者はいろいろと生育環境のことなった子どもたちを保育しなければなりません。
いろいろな視点からモノを捉え、考えて行動することが重要となります。
保育者を目指す本学の学生には、相手を思いやる心やモノやコトに対して心遣いができるようになって欲しいですね。
そのためにも本学の教職員自らもこのことを理解し、マナーやエチケットしきたりを意識しながら学生に対応していきたいですね。
藤田
。

















