今日の心がけ~職員のスピーチ~
聞く耳
2022.05.17
西郷隆盛の遺訓んである「南洲翁遺訓」の第十九ヵ条を紹介しましょう。
「古より君臣共に己を足れりとする世に、治効の上りたるはあらず。自分を足れりとせざるより、下々の言も聞き入るるもの也。
己を足れりとすれば、人己の非を言えば忽ち怒るゆえ、賢人君子は之を助けぬなり」
ここでは、「自分はまだ足りないところがある」と考えていればこそ、部下の言うことも素直に聞き入れられるもの、と説かれています。
さらに、「自分が完全だと思っている時、人が自分の欠点を正すと、すぐ怒るから、賢人や君子というような立派な人は、おごり高ぶっている者に対しては決して味方はしないものである」ということを教えてくれているのです。
◆今日の心がけ◆話は最後まで聞いてみましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
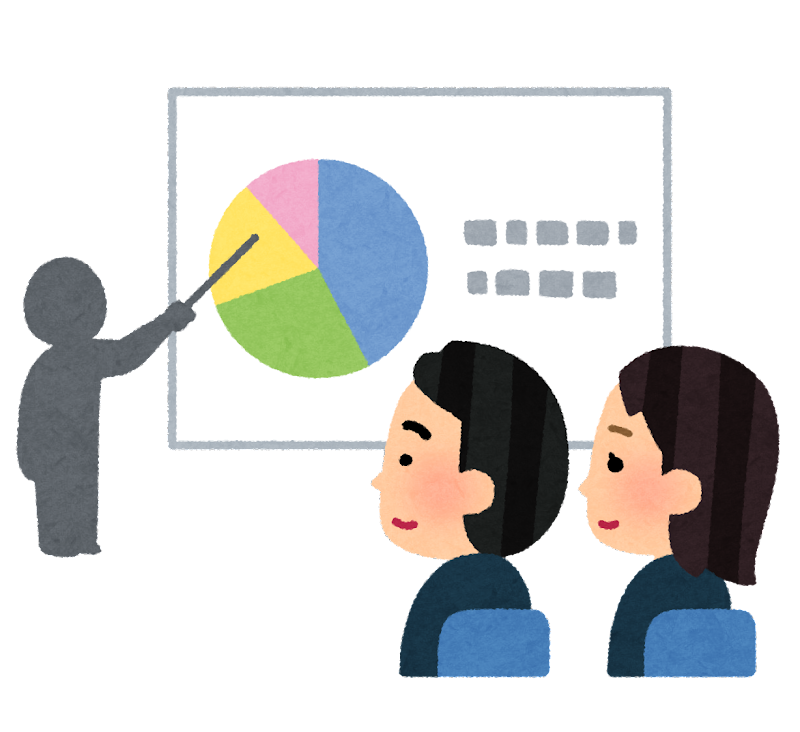
私自身、自分が自信を持って提出したものや、話したことに、指摘や意見をされると、間違っているところに意識が行かずに、まず、自分自身を否定されたような気持ちや、自信を持っていただけに、恥ずかしい気持ちになったりして、素直に受け入れられないことがあります。
以前は、自分よりもそのことに携わっている時間が少ない相手からの意見に対して、自分の方が知ってる・・・という変なプライドがあり、相手が言おうとしていることを先回りして分かった気になり、途中で話を止めてしまうこともありました。
後になって冷静に考えると、長く携わって、自分が一番分かってるつもりでいたのに、なぜこんなことに気付かなかったのだろう?とか、修正してより良いものになり、あのまま出回って恥をかかなくて良かったと反省の気持ちになります。
年齢がどうとか、経験がどうとか、そのようなことは関係なく、自分の行ったことに関心を持ってくれてることや、間違えに気付くくらいきちんと見てくれていること、おとしめるためではなく、業務や状況をより良い方に変えるために、言いづらいはずの意見をくれていることに、感謝するべきなのだと思います。
と分かっていても、また同じような指摘を受けたり、意見をされる状況になると、変なプライドと恥ずかしい気持ちと、色んなことが心をよぎって、素直に受け止められないのだと思います。
ですが、これも今まで何度も経験してきたことなので、このお話の西郷隆盛さんの言葉を心に止め、自分のプライドや心を守るために、言いづらいことを敢えて言ってくれた相手の気持ちを無駄にしてしまわないように、話を聞く時には「まず全部受け止める」ということを心がけようと思いました。
そして、味方を無くさないように、いつまでも意見や提案をしてくれる相手がいてくれるように、聞く耳を持った素直な人間でありたいと思いました。
庶務係 大澤
そうですね。
「南洲翁遺訓」はリーダーとして、人としてどうあるべきかが述べられていますね。
時代を超えて、洋の東西を問わす多くの偉人が同じ言葉を残しています。
上に立てば立つほど謙虚な心と行動が重要だということですね。
現在、世界で起きている様々なことを見ても、まさにこのことができていればと考えざるを得ません。
リーダーが周囲の意見に耳を傾けることができなくなった時には、的確な判断もできなくなります。
世界中の多くの偉人がこれに関する戒めの言葉を多く残しています。
これはそれほど大切なことなのです。
人は知っている「つもり」でも、その知っていることはほんのわずかです。
気が付いている「つもり」でも、それは一部でしかないのです。
的確な判断の「つもり」でも、情報不足から的確でない場合が多いのです。
長野県の元善光寺の住職が書いたとされます「つもりちがい十か条」が、本学の掲示板にも貼ってあります。
高いつもりで低いのが 教養
低いつもりで高いのが 気位
深いつもりで浅いのが 知恵
浅いつもりで深いのが 欲望
厚いつもりで薄いのが 人情
薄いつもりで厚いのが 面皮
強いつもりで弱いのが 根性
弱いつもりで強いのが 自我
多いつもりで少ないのが分別
少ないつもりで多いのが無駄
やはり、人は常に地位や年齢・経験などの上に「謙虚さ」を重ねていかなけれればなりませんね。
我々教職員も学生や同僚など周囲の言葉に耳を傾けられる「謙虚さ」を持って、取り組んでいきたいですね。
藤田

















