今日の心がけ~職員のスピーチ~
あれはどうなった?
2022.05.17
とある職場での、Kさんと部下のS君の会話です。
Kさんから「あれはどうなっている?」と突然尋ねられたS君。
一瞬、<あれってなんだろう>と戸惑いながらも、自分なりに想像を巡らせて、心当たりの仕事内容について報告しました。
Kさんは見当違いの答えにイライラして、「それじゃない、別件についてのことだ」と注意しました。
「あれ」の次は「別件」です。<もっと具体的に言ってくれたらいいのに>とS君は不満を募らせました。
こうした会話の例は日常よくあることです。
上司の立場としては<言わなくてもわかるだろう>という姿勢ではなく、きちんと内容を伝えるべきでしょう。
S君にも落ち度は無かったでしょうか。「あれ」も「別件」も、本来は、上司から確認される前に自分から報告すべき事柄だったかもしれません。
不満や不足を感じた時こそ、相手を責めるより、自らを振り返るチャンスとしたいものです。
今日の心がけ:自省する習慣を作りましょう
出展(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
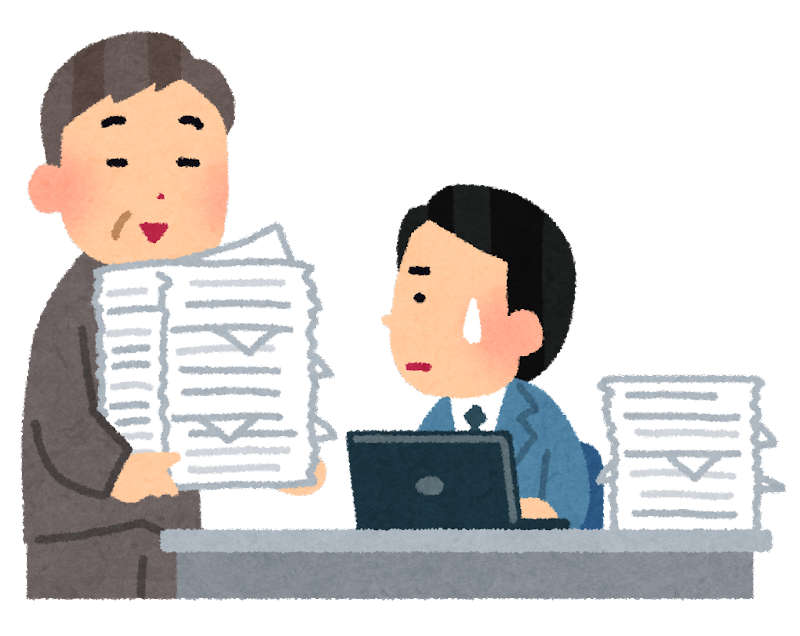
抽象的物言いやこそあど言葉で、大なり小なり災いの種を撒いてしまったことは誰もが経験していることでしょう。
コミュニケーション過多も不足も人間の業と言えるもので古今東西いろいろな諺や警句、格言が伝えられています。
長年連れ添った連理の枝では「あれ」「これ」「それ」が意味を持った言葉で通じますが、他人にはなかなかわかりづらいものであります。
間違いを起こさないためにも、名詞を使用しての会話がよろしいようです。
日本の諺で「背負うた子に教えられ浅瀬を渡る」がありますが、これこそまさにこの文章で喩えられることです。
自分以外は全て師であり、人は幾歳になっても学び教わることが多いです。
省みつつ事故の成長につなげていきたいと思います。
以上
進路支援担当 奥貫
そうですね。
「あれ」「それ」「これ」は家庭でも職場でも飛び交っていますね。
特に年齢を重ねた人におおくなりますから「年齢のバロメーター」とも言えます。
身近な人(夫婦)などでは日常的(ルーティン化)になっていることはあまり問題にはなりません。
かつては夫は家庭で妻に「おい」「あれ」「それ」以外の言葉がなくても暮らせたと言われます。
しかし、この「あ・そ・こ」はお互いにいろいろと食い違いを生じさせます。
今では「あれ」も「それ」もいろいろなものがありますから、これでは通じません。
ここには相手は「分かっているだろう。知っているはずだ」と「だろう」「はずだ」の不確かな了解があります。
これににたもので「いつもの所で」「いつもの時間」「いつものように」などの「いつもの」もあります。
これなどは判断を相手にゆだねた「察してほしい」といった「甘え」があるようにも思えます。
土居健郎先生の『「甘え」の構造』を読んだことを思い出しました。
職場では、できる限り具体的に物事を表現してコミュニケーションギャップを起こさないようにしていきたいですね。
藤田

















