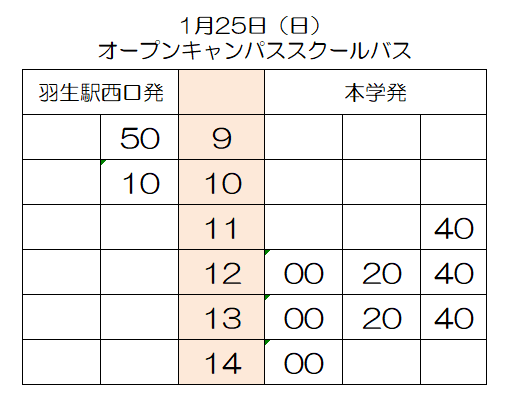今日の心がけ~職員のスピーチ~
方言を愛することは自信を持つということ
2015.07.01
『職場の教養』(社団法人倫理研究所)「言葉の力」を読み、
今日の心がけとして、“方言を大切にしましょう”
と言いたいところですが、
しっかりと方言や訛りのある北海道出身の私にとっては、
方言を大切にすることの意味を 未だ理解できていないような気がします。
子供の頃、綺麗な言葉=標準語と教わり、
現代の東京の言葉(江戸弁ではない)がそれに近いと
記憶していたと思います。
標準語がどういう言葉なのかは、
テレビなどのメディアを通して耳にすることはできます。
そのため、いつのまにか標準語に近い言葉で話すことを
心掛けていたような気がします。
それでも、私が上京した学生の頃、
北海道弁を指摘されて馬鹿にされたことがあり、
意識して言葉を変えたことがあります。
同様に、栃木や茨城の出身の友達も、
独特な地元言葉のイントネーションをからかわれていました。
ただ不思議なことに、当時でも関西弁は、
いわゆる“市民権”を得ており、大阪出身の方は堂々としていました。
また、流行りかとは思いますが、
「~じゃん」という神奈川から静岡にかけての方言は、
お洒落な言い方として誰もが使っていました。
言葉の力は大きいものですが、方言の力とは何でしょうか?
日本古来の言語文化がその土地の風土を表している…
だから良き文化は大切にしなければならない、 ということでしょうか。
津軽弁の影響を受けているであろう北海道南部の方言を話す人は、
標準語圏では、極めてマイノリティな存在ですが、
昨今、差別意識を正していく世の中で、
田舎言葉を大切にしようという雰囲気が高まっているのは、
方言を大切にしなければならない本当の意味なのかもしれません。
小さな島国で、これだけ多様な言葉があることは、
とても面白いと思います。
おそらく鹿児島弁を話す人と津軽弁を話す人では、
会話を通じ合えることが難しいでしょう。
最近知ったのですが、私が今住んでいる熊谷にも、
「~なん?」(「~なの?」ということ)という訛りがあるそうです。
寺山修司の短歌に
「ふるさとの訛りなくせし友といてモカ珈琲はかくまで苦し」
というのがあります。
大げさかもしれませんが、周りへ必死に合わせようとしていたことに、
どこか、自分を消すことの苦々しさがあったのかもしれません。
郷里を離れて地方を見つめ直すことで、
その意味の大切さに触れていきたいと思います。
事務局 係長(進路支援担当) 中村 周