今日の心がけ~職員のスピーチ~
心の幅を広げる
2022.04.01
元外交官で、作家の佐藤優氏は、小説を読む重要性を次のように述べています。
「人間が個人的に経験できることは限られている。そのため、優れた小説で代理経験を積んでいくことは人生を確実に豊かにする」
小説に登場する人物の心の内を「代理経験」することで、「他人の気持ちになって考えることが出来るようになる」というのです。
職場だけでなく、家庭や地域で、私たちは様々な人と関わり合って生きています。
時には、意見の違いから衝突することもあるでしょう。
人は生まれ育った環境は異なり、様々な価値観を持っています。
自己の人生経験で培った尺度だけでは、相手を理解することはできません。
読書を通じた「代理経験」で、相手の立場になって考える度量が大きくなるのです。
「毎日忙しく、本を読む時間がない」という人もまとまった時間ではなくても、通勤電車の中、人を待つ間、寝る前の5分など、意識して本を読む習慣を身に着けたいものです。
今日の心がけ◆ 本を読む時間を作りましょう(「職場の教養」一般社団法人 倫理研究所より)
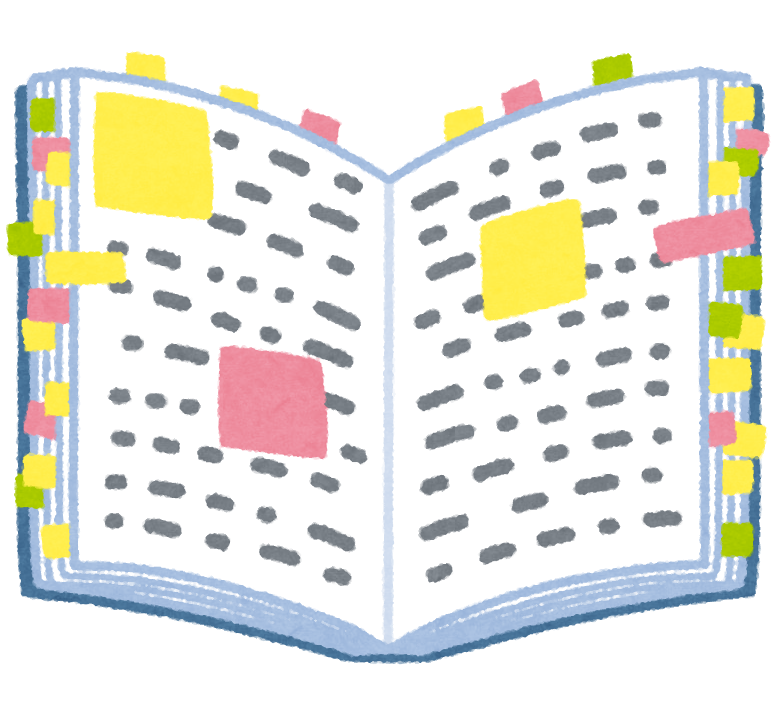
「本を読むべき」と一般的によく言われます。
ビジネス書や学術書などには「知りたいことがあるから読む」という明確な理由があると思います。
しかし小説については、本があまり好きではない人にとって「読む意味はあるのか?」という問いにつながるようで、学生からもそのような質問を受けることがあります。
読書の効用は様々な分野で研究されているようです。
神経科学分野の研究で、小説などのフィクションを読んだ時に、その出来事を実際に自分が体験した場合と同じ脳の部位が反応することがわかったそうです。
文中にある「代理経験」が、実際に脳内の反応として起きていて、登場人物と同じような気持ちを感じるための脳のトレーニングを積み、共感力を向上させているとういうことになるようです。
共感力のほかにも、読解力を身につける、教養や雑学が身につく、語彙力が増す、文章を書く力が伸びるなど、小説を読む効用は多くあげられます。
読書好きな学生には、楽しく充実した時間を過ごせる場として、本があまり好きではない学生にも、本に親しむ機会を提供する場として、本学の図書館が機能できるよう、様々な工夫を凝らしていきたいと改めて感じました。
図書館 大木

















