今日の心がけ~職員のスピーチ~
対面販売を通して
2023.10.07
東海地区でぶどう園を経営するUさんは、全国区の賞を受賞する品質のぶどうを育て、その種類は三十五品種に及びます。
インターネット販売も行ないますが、売上の九割以上を占めるのが、ぶどう園に隣接する直売所での対面販売です。
直接、お客様からの声をもとに品種を仕立てて、〈あの人に喜んでもらおう〉と顔を思い浮かべながらぶどうを作ります。
現代では多様な情報ツールを通してお客様と接点が持てます。
それは販路の拡大にもっながり、多くのお客様と出会うきっかけが広がります。
その中で、Uさんの手法は、多くのお客様に届けたいだけでなく、〈あの人に喜んでもらいたい〉という究極のお客様本位の形といえるのかもしれません。
生産者と消費者が直接顔を合わせるケースは、あまり多くはないでしょう。
どのような手法でも、相手を思って取り組む姿勢は、その人に通じるものです。
サービスや商品を通じて、間接的にお客様と関わる職場もあります。
どのような職場であっても、お客様の喜びを想像しながら、仕事に取り組みたいものです。
今日の心がけ◆誰かの喜びにつながるか考えてみましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
対面販売と言っても、Uさんの様に生産者自ら商品を販売するのは、流通先の店頭で販売業務を担う人がお客様に商品を紹介することとは違っています。
直接お客様の声を聞き、何を求めているのか、何が喜ばれるのか、年齢や性別など、どのようなお客様なのか、Uさんご自身でマーケティングが出来ている事が大きいと思います。
インターネット販売や流通先の店頭販売では、売上データや項目別統計の数字だけしかわからず、お客様そのものがわからないので、Uさんが重きを置いている対面販売は誰かの喜びに繋がる強みであると感じました。
このことは、本学の業務内容に置き換えても同じことが言えると思います。
事務職とは言え、先生や学生を中心とした業務ですが、学籍番号、氏名、クラス、出身校、実習先、欠席数や成績など、データのみで事務処理を進めることは出来ても、それで何も問題もなく進められているのかは違うのではないかと思います。
やはり、学生一人ひとりと直接向き合い、話を聞き理解していくことで学生が何を求めているのか、何に困っているのかと考えることも大事だと思います。
2年生は殆どの学生が、全ての実習を終え、いよいよ就活となります。
残り少ない本学での時間が有意義なものとなるよう、しっかりと向き合い力になれたらと思いました。、
実習指導係 栗原
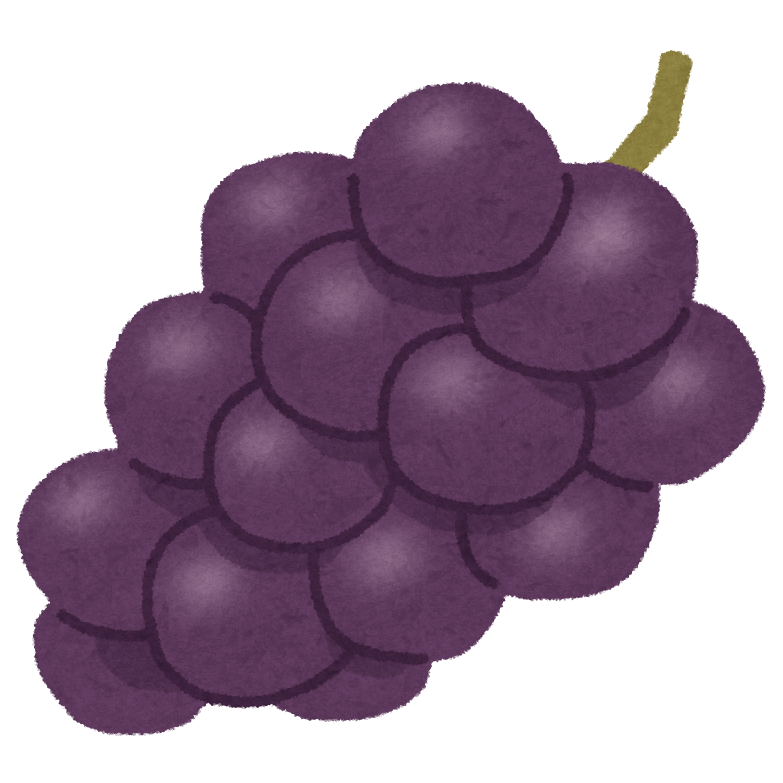
そうですね。
現代はインターネットを通じての販売が増えています。
売る側も買う側も時間と手間を省けるからです。
しかし、その手軽さとともに、そこで失っているものもあります。
モノを見て、嗅いで、触れて、その場の雰囲気を感じてといった人間の五感による喜びです。
送られたものを食べて美味しいと感じることはできても、その背景を感じることはできません。
現在はこれを少しでも防ごうと生産者の写真や地域の説明文を入れたモノが多くなっています。
しかし、それでもその土地の空気や匂いなどまでは伝わってきません。
また、その場で口にする場合と送られて物を口にする場合の味も異なります。
お互いが実際に顔を見合わせて行う現実と仮想現実の世界で行う場合とでは全く異なった感覚になります。
簡単にメールで連絡できる世の中ですが、ちょっとした手紙やメッセージカードを受け取った時の気持ちはどうでしょう。
人の思いが伝わるのも視覚と聴覚、嗅覚、触覚などの五感を通してですからね。
保育者を目指す学生には子どもとの触れ合いが大切となります。
そのふれあいの大切さを理解するためにも、教職員自らが心を感じながら対応することが大切です。
VRが進む時代だからこそ、アナログの心のふれあいが感じられる対応が重要ですね。
藤田

















