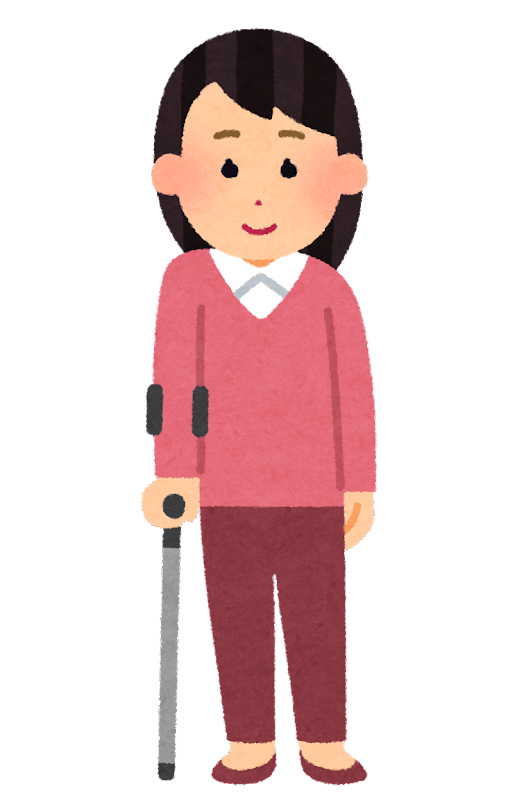今日の心がけ~職員のスピーチ~
杖を使う生活
2023.08.09
人は年齢を重ねるにつれ、体の不調も多くなるものです。
五十代後半のIさんは膝の具合が悪く、医師に手術を勧められました。
術後は、膝を曲げることが難しいため、杖を用いた生活が始まりました。
Iさんは<杖があるから、歩くにはそれほど困らないだろう>と思っていました。
しかし、いざ生活してみると、階段を上がる大変さ、下りる時の怖さ、
長時間に亘って歩く困難さを思い知りました。
Iさんは杖を使った生活をするうちに、<自分はそのような人たちに対して、
これまで温かい目を向けてきただろうか>と、考えるようになりました。
「相手の立場に立って考える」とは、よく言われる言葉です。しかし、Iさんは、
そのつもりになっていただけだったのです。
私たちもIさんのように、相手をおもいやっているつもりに、陥っていることが
多々あるかもしれません。街中で困っている人を見かけた際には、手を差し伸べる
優しさを持ち合わせたいものです。
今日の心がけ◆思いを行動に移しましょう
『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より
痛みや体調不良は言わないとわかってもらえない場合があります。
言わないと相手が誤解をすることがあります。
自分しか痛みはわかりません。最近では無理ができなくなったので言うことも
あるようになりました。
できてたこともできなくなりつつあるので、いろいろな方法で行動に移したいと
思います。
事務局係長 田中 淳一
そうですね。
他人の痛みを自分のことのように感じるのは「共感力」の度合いによるものでしょうね。
子どもや親や家族など「身近な者に対しての痛みは感じやすく、見知らぬ人に対してはそれほどの痛みは感じないということです。
「相手の立場に立って」とはよく言われることですが、これはほんとうに難しいことです。
相手と同じ状況や状態を経験していれば、「相手の立場に立つこと」も可能となりますが。
「我が身をつねって人の痛さを知れ」や「子を持って知る親の恩」などが言われていますね。
このことからも共感力を高めるには経験が必要だと分かります。
保育者を目指す本学の学生にはこの共感力の高い人になって欲しいですね。
そのためにも周囲の物事に「関心を持ち」「気づく」ことから「行動する」ことが重要ですね。
学生サポートをする我々教職員が学生対応においても模範とならならなければなりませんね。
藤田