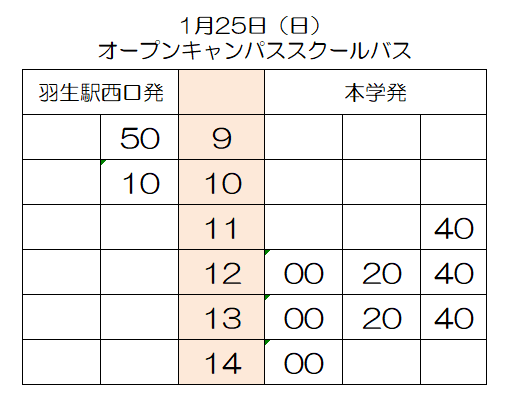今日の心がけ~職員のスピーチ~
言葉の効用
2023.08.06
社会生活を送る上で私たちは、自分自身の思いや考え、感情など頭や心で描いたものを「言葉」や「文字」、あるいはお辞儀、握手、笑顔などの形に変えて相手に伝えていきます。
良好な人間関係を築くためには、相手の立場や年齢などによって言葉遣いや態度など接し方を変えることも必要でしょう。
言葉は昔から「言霊」といわれ、情報伝達手段であるだけでなく、心と心をつなぐコミュニケーションツールとして、想像以上の威力を放つ時があります。
「あの人のひと言で傷ついた」というマイナスの力もあれば「あの人のひと言で救われた」と、プラスの威力を放つことがあるのも言葉です。
「言葉遣いは心遣い」といわれるように、言葉には人柄が現われるものです。
使い方次第では誤解を招いたり、違う意味で捉えられたりすることもあります。
職場において身だしなみや態度を重んじるように、自らの言葉遣いが業務にふさわしいものかどうかを、再確認することも必要だといえるでしょう。
今日の心がけ◆普段の言葉遣いを再点検しましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
文中の通り、人からの言葉や態度で嬉しくなったり、悲しい気持ちになったりします。
それは、普段自分からも発せられる言葉で相手を傷つけてしまうことがあるかもしれません。
普段どんなことを思っているかで、行動やあいづちもこの人には丁寧なのに、違う場面では適当だなと感じたりすることがあるかもしれません。
特に嫌だった経験は心に残ります。
相手を思いやれるかで、口から出てくる言葉も変わってくると思います。
言葉遣いで、お互いが気持ちよく仕事ができたり、人間関係が良いことで円滑に進むことができると思いますので、私自身も相手への気遣いができているか、もう一度振り返りたいと思いました。
荒井文菜
そのとおりですね。
言葉の「言」は文字を2つに分けると「口と心」となり、「言」は口から出た心となりますね。
発する言葉によってその人がどのような人であるかを無意識に判別するのも、このことからかもしれません。
その言葉も改まった状況ではなんとか取り繕うことができても、トッサの場合には日頃の生活が出てくるのです。
挨拶はその典型的なものと言えます。
明るい笑顔で心から口から出す人、とりあえず口から出す人、言葉も視線も向けない人など様々です。
どうしてこのようになるのかを考えてみると、生活環境が最も影響しているのだと考えられます。
何故ならば、言葉を習得するには自分の周囲の人の話す言葉を真似することから始まります。
その習得した言葉を使うことによって、その環境で生活することができるのです。
同じ内容を話しても、どのような言葉で表現するかは人によって異なります。
これも日常の生活経験によるものだと考えられます。
“My Fair Lady”のイライザや”Pretty Woman”のビビアンの言葉遣いや服装の変化からも分かる通りです。
言葉が重要なのは「言」と「聴」とで成立するコミュニケーション”Communication”が「心」と「心」の共有だからです。
言葉と心は直接的に結び付いていますから、日常発する言葉があなた自身を作っています。。
「あなたはあなたが使っている言葉でできている」(ゲイリー・ジョン・ビショップ著)もよく言われていることです。
受け取る言葉は聴覚でだけではなく、表情やしぐさや服装などから視覚からも同時に受け取ります。
どのような折にどのような言葉遣いをしているかを意識して思い出してみてください。
服装や態度、表情とその時の感情など全てが常に連動しています。
信頼される保育者を目指す本学の学生が、TPOの合わせて適切な言葉遣いができるようになってもらいたいものです。
そのためにも学生をサポートする教職員が学生の手本となる言葉遣いをする必要がありますね。
藤田