今日の心がけ~職員のスピーチ~
読書のすすめ
2023.06.14
哲学者の野矢茂樹氏は、著書の中で「国語力は愛だ」と述べています。
それは相手のことを考え思いやる態度と、何よりも相手と分かり合いたいという気持ちが、高い国語力に結び付くからだといいます。
人とわかり合うためには、自分の言いたいことをまとめる力だけでなく、相手のことを考え思いやる態度が求められます。
加えて、他者が発する言葉の意味を読み取ろうとする姿勢と理解力が必要になります。
それは、多くの質の高い文章に接すること、つまり読書をすることで高めることができるのです。
今日の心がけ◆国語力と思いやりに磨きをかけましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
ガイダンスで高校生に話をするときに、高校時代にやっておいたほうがいいことの一つとして、国語力のアップは重要だということを伝えています。
保育者の仕事は、想像力が非常に大切です。
大学で学んだ知識だけでカバーすることは難しく、想像力を駆使しあらゆる場面を想定して臨機応変に対応することが常に求められます。
そして文章を書く場面も多く、国語が苦手な人にとっては苦痛な仕事なのではないか、と感じるほどです。
国語力が保育の仕事にとってなぜ大切なのかを高校生に説明し、読書が苦手という人にはまずは絵本や童話からでいいので読み始めることを勧めています。
考えてみると、私の今の仕事も国語力が必要なのかもしれません。
私たちが伝えたい情報と、高校生が求めていることは時に違う場合があります。
こちらから伝えたいことを説明することは大切ですが、それよりも、相手が知りたいことを想像することのほうがより大切な気がします。
求められていることを、わかりやすい言葉で伝えることは年齢や性別が違うことで難易度があがります。
誰に対しても伝わりやすい言葉で話ができるよう、これからも質の良い本をたくさん読み、私自身の国語力に磨きをかけていきたいと思います。
入試広報係 西山
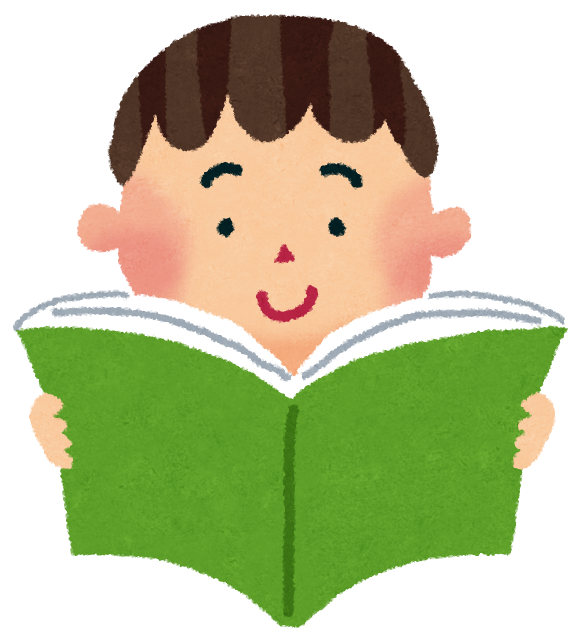
そうですね。
GfKジャパンによる「読書頻度に関するグローバル調査」(17ヵ国で2017年実施)の結果、日本は17ヵ国中15位だとのことです。
株式会社アイスタット(2022年)の「活字離れ」の調査によると「活字離れした」と感じる割合が8割に達し、20~30代が多いという結果だそうです。
全国学校図書館協議会と毎日新聞社が毎年6月に全国小中高校で実施している読書に関する調査結果でも中・高生になるに従いと読書量が減っているようです。
考えさせられますね。
人は学ぶ動物です。一生学びの佳奈に生活していきます。
言葉はまさに「まねび」から修得するモノです。
「まねる」ものがどのようなものであるかによって、人のモノの考え方や感じ方は作られます。
脳の発達過程から見ても幼児期から、15歳位まで、20歳位とそれぞれの部位の発達があるでしょう。
このそれぞれの時期にどれだけの文字や言葉を通して、どのようなめぐり逢いがあるかが、人を創ると言っても良いかもしれません。
このため、感情を読み取り、理性で判断できる人になるためにも、この読書は不可欠なものと言えるでしょう。
人は社会的動物です。
自分の欲望追求だけでは生きていくことは難しくなります。
良好な人間関係なしには生きていけません。
この良好な社会関係を構築していくためにも、それぞれの発達に応じて感性を磨く必要があります。
人は自らで経験・体験できるものはほぼ限られます。
読書はその限られた体験や経験を他人の経験・体験を通して、さらに広く深く学ぶことができます。
そのため、信頼される保育者を目指す本学の学生には、ぜひとも古典・名著と言われる書籍をはじめ多くの読書に臨んでもらいたいですね。
恒例となった図書館主催「読書感想文コンクール」にも多くの応募者があると良いですね。
藤田

















