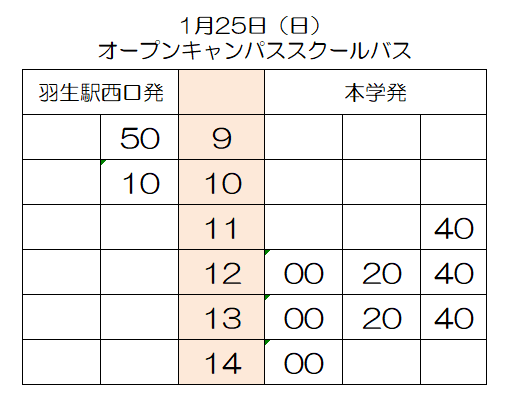今日の心がけ~職員のスピーチ~
電車の中で
2023.04.13
ある満員電車での出来事です。
間もなく次の駅に到着しようとしていた時、車両の真ん中あたりの乗客が「すみません、すみません」と叫んでいました。
次の駅で降りたい様子でした。
しかし、発する言葉が「すみません」だけで、耳にイヤホン、視線はスマートフォンの乗客には、その思いが届きません。
結局、停車後に、押し合いへし合い、人垣を無理やりかきわけて進みました。
周囲から迷惑そうな視線を投げかけられて、ホームへ降りていったのです。
意思疎通を図るには、一方の意思が適切に表現され、相手がしっかりと受け止めることが必要です。
この乗客の間では、それがうまくいかなかったのです。
もし「すみません」の後に「降ります」の一言を付け加えていたならどうでしょう。
何をしたいのかが直ぐに伝わり、違った反応が返ってきたかもしれません。
イヤホンを耳にしていた乗客は音量を少し下げれば、声が聞こえやすくなったでしょう。
視線を少し上げれば視野が広がり、周囲の状況も察しやすくなります。
少しの工夫と気配りで、コミュニケーション能力を高めていきたいものです。
今日の心がけ:しっかり話し、聞きましょう
満員電車ともならば意図せず、中へ中へと押し込まれ、降りるに降りられない経験は、おそらくどなたにでもあることでしょう。
かと言って、出入口付近に陣取り、駅についても踏ん張っている人を見るたびに残念な気持ちになります。
もし、降りたくても降りられなさそうな状況の時は、次のようにしたらいかがでしょう。
電車内で降りたい時は、大きな声で『降ります!!』と伝えましょう。
「ありがとうございます!」を付け加えると、周囲の心証もよく、スムーズに道を譲ってくれるはずです。
さて、声の大きな人や元気の良い方ならば、意図するところははっきりと伝わるものですから、これはわかりやすいでしょう。
逆に、控えめだったり声が小さかったり、しぐさで感情をあらわすような学生も近頃は多くおります。
こどもに対しては、なかなか伝わりません。
結果、叱責されて自信を無くしてしまったり、ストレスを抱えたりする方がいるようです。
では、私たち大人が何をすべきか、ということになりますと、自分自身でしっかり話すことができるように指導していくことが必要だと考えます。
とは言え、その人のアイデンティティですから、アドバイス程度にとどめ、あとは自分自身でしっかり見聞きする癖を身に付けてほしいと思います。
以上
出展(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
進路支援担当 奥貫
かつて電車の中でこのような風景は良くありましたね。
以前は「降りる人を通してやれよ」と大声で助けてあげる人もいました。
しかし、ここでもあるように近頃は他人に意識を払わない人が多くなってきたように感じます。
周囲に関心を寄せていれば自分自身の位置と行動の取り方がハッキリとします。
これは人間の「知覚・判断・推論・決定」などの認知が衰えていることだと考えられますね。
かつて日本人は「察する」「以心伝心」が得意と言われてきました。
このことが必ずしも良いとは言えませんが、他人や周囲に関心を持って自ら適切な行動をとることができていました。
それもおおげさでなく、恩きせがましくなく、「さりげなく」です。
この「さりげない気遣い」ができる人はいろいろな人と良い人間関係が構築できるのです。
この満員電車の中の出来事も「いつか自分も同じ立場に」と考えられる人であれば、「すみません」の言葉と態度から状況を判断できたはずです。
駅に到着すれば「降りる人もいるだろう」といった本当にアタリマエの状況すら認知できないのは残念です。
「信頼される保育者」を目ざす本学の学生は、この認知能力が重要です。
そのためにもサポートをする教職員がこの能力を発揮して、学生が有意義な大学生活を送れるよう、手本となって示したいものです。
藤田