今日の心がけ~職員のスピーチ~
昔話から
2023.02.28
「むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。
おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へせんたくに行きました。」
これは、昔話「桃太郎」の最初の一節です。
Kさんは、小さい頃から「しばかり」とは、「芝刈り」だと、疑いもなく思っていました。
ただ、<芝を刈るのに、野原ではなくなぜ山なのだろう>との疑問を抱いていました。
ある時、友人との雑談の中で、「しばかり」とは「芝刈り」ではなく「柴刈り」だということを知ったのです。
「柴」とは、山野に自生する小さい雑木です。
「柴刈り」とは、柴を薪にするために、その枝を切ったり集めたりすることです。
Kさんは、本当の意味を知り驚きました。
そして、自分ではそうだと信じている事柄の中にも、実際には全く違うことがあるのだと、思い知りました。
この件で、<わかっているつもりでも、そうではないことや、自分の思い込みから誤解していることが他にもあるかもしれない>と考えを新たにしたのです。
私たちも、疑問に思った時には、検証することが肝要です。
今日のこころがけ◆知っているつもりはやめましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
知らないことであれば、もちろん調べたり確認すると思います。
しかし、知っていると思うことは、注意する意識が薄く、このように間違って覚えたままのものもあるかもしれません。
また、知っていることでも、時には時代や相手など周りの環境で変わっていくこともあります。
例年通りの業務だとしても、何かをする時には、よく係の職員や部長に確認・相談をしていますが、それは対策の一つになると思います。
他の人に見てもらったり話を聞くことで、自分の経験の中では知らなくて気づけなかったことを教えてもらい、ここは直した方がいい、こうしたらよりよくなるなど、気づくことがあります。
教務も部署異動により今年度担当者が変わりました。
人が変わると今までの仕事も新たな目で見られ、間違いや不足などに気づき、改善できるものもありました。
同じことばかり繰り返すのでは変化がなく、知っていると驕りも出てきてしまうため、定期的な人の循環は必要かもしれません。
自分自身も知っていると過信せず仕事に取り組み、適宜確認して間違いがないように気をつけるように努めていきたいと思いました。
相馬
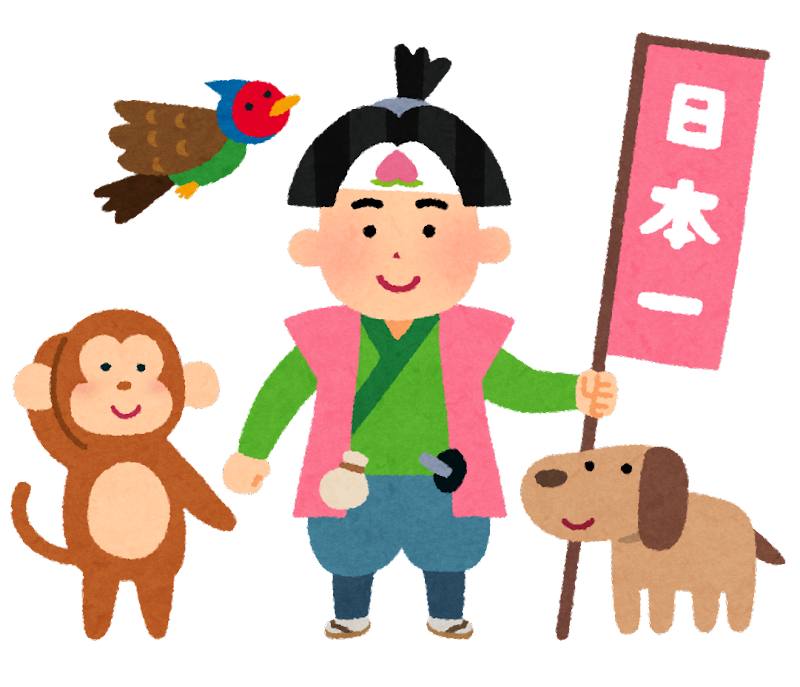
そうですね。
自分のこれまでの経験や体験の中で、知っているツモリになっている場合がありますね。
よく話題になる唱歌「ふるさと」歌いだしの「うさぎおいし、・・・。こぶなつりし・・・」を美味しいウサギと思っていたことなどです。
「君が代」の「さざれ石」もどんな石なのか勝手に想像していただけで、実際に見た時は想像と異なっていたので驚きました。
このように体験や経験が不十分なことを「つもり」で行うことは危険ですね。
その体験や経験も個人だけの狭い範囲だけのこともありますからなおさらです。
ここではよく確かめて確実なものにしていく努力が重要ですね。
職場においては自分自身の行動ひとつ一つが周囲にいろいろな影響を与えます。
誰か一人の勘違いや小さなミスが波紋のように大きく広がることもあります。
自分の力や知識・経験が足りない場合でも、周囲の人のそれを借りてこれを埋めることができます。
そこでコミュニケーション(communication)が重要とななります。
”common”(すべての人が共有する)意味からも、お互いに知識や情報を共有することが大きな力となるからです。
このコミュニケーションが円滑であれば「つもり」での間違いはかなり防ぐことができます。
特に保育にあたる本学の学生は「つもり」保育はありえません。
そのためにもしっかりと「聴く」、恥ずかしがらずに「訊く」ことがスムーズにできるようになって欲しいと思います。
そのためにもサポート役の教職員が実行している日常を見せることが大切ですね。
藤田

















