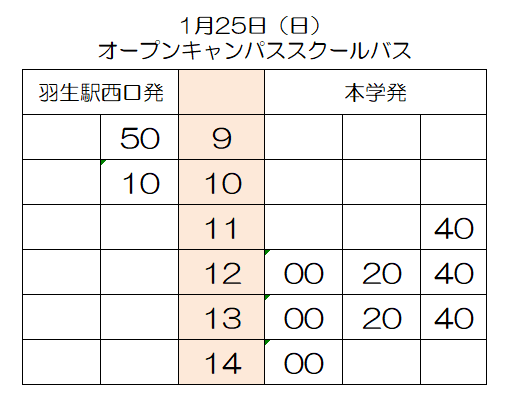今日の心がけ~職員のスピーチ~
ものに礼を尽くす
2023.02.17
私たちは日々の生活の中で、様々な「もの」に囲まれています。
「もの」からは、機能や働きによる便利さや、その存在から得られる心の安らぎなど、たくさんのメリットを受けています。
そうした反面、普段、「もの」に感謝することはあまりないかもしれません。
豊かさに慣れて、使い捨てが当たり前だと思う人もいるでしょう。
古来日本では、針供養や人形供養など、「もの」を労う供養を行なってきました。
現在は、八月三日の「ハサミの日」といった記念日などもあります。
「もの」に対する感謝を供養という形で行うのは、日本独特のことといえるでしょう。
美容室を経営するSさんには、三十年来愛用しているハサミがあります。
定期的なメンテナンスを施し、大切に扱っています。
「大事にすると、精一杯に働いて、髪の毛をきちんとカットしてくれるのですよ」とSさんは言います。
「ものには魂が宿る」との思いで大事にしてきた古くからの慣習を忘れずに、身近なものに感謝し、使った後は礼を尽くしていきたいものです。
◆今日の心がけ◆ものへの感謝を表わしましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
時々、学生の忘れ物ボックスを見て、切なくなる時があります。
私だったら気になって探しまくったり、見つかるまで気が気じゃなく、眠れないだろうなと思う物まで、ずっとボックスに入ったままです。
結局、持ち主が見つからないままというものが殆どです。
絶対に誰かが買い、使い、さっきまで持ってたはずの物なのに、数分後には持ち主のいない、要らないものになってしまっています。
自分が欲しくて手に入れた物のはずなのに、そんなに簡単に手放せることが、私には理解できません。
物が簡単に手に入り、溢れてる時代だからということでは、納得できないほど、粗末にしすぎているように感じます。
このお話のように、道具や物は生き物ではないので命はありませんが、魂は宿ると私も思います。
だから、無意識に道具や物に対して、「この子」と呼ぶ時があります。
私以外でも、そのように呼んでいる人は沢山います。
以前に針供養のお話を読んでから、私自身、物を大切にしたり感謝したりするから、道具がよく働いてくれるのではなく、愛着があったり、使いやすかったり、もっともっと使いたい、持っていたいという自分の気持ちが、長く使えるような状態を作っているのだと思っています。
これから、子ども達に大切なことを教える立場になる学生のみなさんには、今、自分が不自由なく過ごせているということに気付いて、もっと物にも周りの人にも感謝して、大切にできるようになって欲しいと思います。
庶務係 大澤
「モノを大切にしなさい」「ツギを当てて着(履き)なさい」「もったいない」などの言葉はいつ消えたのでしょうか?
ノーベル賞受賞者マータイ女史によって世界の共通語となった「MOTTAINAI」が話題になったのは今から20年近く前になります。
”SDG’s”が話題となる今、この「もったいない」の言葉を大切に実行したいですね。
今、テレビ番組で「断捨離」が人気となっていますが、これは不要なモノを持ち過ぎた結果です。
モノへの執着を亡くし、シンプル生活を求めるものですから、捨てるというよりは余分なものを手に入れないことです。
こんなことから中学校で学んだ「行く河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。」の鴨長明の方丈(約3m四方)の庵で心穏やかない静かな生活や「徒然草」の兼好法師が思い出されますね。
モノのない時代にはモノを大切にし、使用できなくなった時には感謝の気持ちで見送る日本人の心の美しさがあります。
人間以外の動物のの供養塚が祀られ、針供養をはじめとするモノへの感謝の気持ちを供養として表しています。
一方、近代以降の社会では人間にとって都合の良いモノ造りから地球に大きなダメージを与えています。
人間も自然の一部であることを忘れず、分をわきまえた行動をとることができれば良いのですが・・・。
現在もあり余ったものを持ちながら、さらに他人の物まで奪おうと地球上ではいろいろな事件が起きています。
保育を目指す本学の学生には身の回りの人やモノに感謝の気持ちで接し大切にしてもらいたいですね。
藤田