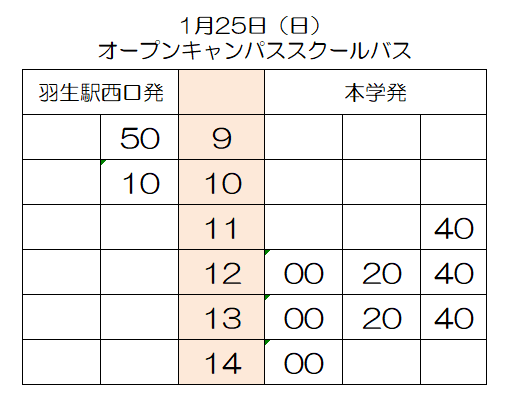今日の心がけ~職員のスピーチ~
会話はキャッチボール
2023.02.07
日々、何気なく交わしている会話には、その人なりの癖が現れるものです。
その一つが長話になってしまうことです。
人の話を聞いていて、「話が長いな」「同じことを何度も言っているな」などと感じることはよくあります。
では、自分自身ではいかがでしょうか。
話したいことがあるときは、相手の話を聞こうともせず、一方的に話してしまうものです。
しかし、せっかくの話も長すぎると、共感を得られないでしょう。
もし、会話の中で「自分ばかり話しているな」と感じた時は、相手に話を振るようにしましょう。
「〇〇と思うんだけど、〇〇さんはどう思う?」とm話の主導権をバトンタッチするのです。
大勢に向かって話をするスピーチと違い、会話はキャッチボールです。
会話のボールは一人だけで握らず、相手に投げてみましょう。
闇雲に投げずに、「そろそろかな」と、タイミングを見計らうことが大切です。
先ずは、キャッチボールの相手の存在を意識することが、改善への第一歩です。
30年ほど前に旅を始めたころ、同宿の人が大阪の人でした。
彼は本当によく喋る人で、寡黙な私には驚異の人でした。
ご飯の時にものべつ幕なしに話すのには、まさに芸人といった風情でもありました。
ただ、話の主導権を握るあまり、握りすぎて他の人が話す事柄に対してもそれを奪ってしますことがありました。
学生も結構同じような世界があるようです。
おとなしい学生は、声が大きく元気な学生に押されがちのように見られますが、自分の意見はしっかり持っています。
就職は最終的に本人の意思です。
本人の意向を傾聴し、過去どうこうや噂、又聞きに左右されずに事実を伝えて、希む就職に結び付けられればと考えます。
以上
出展(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
進路支援担当 奥貫

そうですね。
会話はキャッチボールです。
会話はまず聴くことから始まりますね。
「話し上手は聴き上手」と言われますからね。
聴き上手、話し上手になるには「相手に関心」や「話に興味」を持つ必要があります。
つまり、相手の立場になって聴く、話すことが重要です。
キャッチボールですから、ボール(話)のスピードや方向もしっかりと見定めることが必要です。
そのボールを受けたり投げたりする力も見定めなければなりません。
相手がどのレベルにあるのかを見る力も必要です。
「人を見て法を説け」と言われるように、相手に合わせたボールの投げ方や種類も決めなければなりません。
そのためには技術的レベルの高い人がレベルの低い人に合わせるとキャッチボールはスムーズになります。
会話も人との付き合い方も同じでしょう。
どのような人とも、どのようなボールにも対応できるように力をつけておくことが大切です。
幼児から大人までに対応する必要のある本学の学生がこのことを理解してくれると良いですね。
そのためにもサポートをする我々教職員がキャッチボールの大切さを示していきたいものです。
藤田