今日の心がけ~職員のスピーチ~
梅雨を晴れやかに
2020.01.20
「五月雨」という言葉をご存じでしょうか。
一般的な辞書によると、概ね「旧暦の五月に降る長雨」を五月雨と称しています。
今の五月ではなく、旧暦の五月のことですから、実は梅雨と同義です。
今も昔も、長雨の時季は、うっとうしさを感じるものです。
しかし、先人は長雨を「さみだれ」という美しい響きで表現することで、少しでも心が曇らないようにしていたのではないでしょうか。
現代に生きる私たちも「雨の日もいい」と声に出して、自分に言い聞かせることで、晴れやかな気持ちに転じられるかもしれません。
実際に、梅雨にまとまった雨が降らなければ、ダムは渇水状態になってしまいます。
農作物の育ちも悪くなります。
心を曇らせてしまうと、行動も鈍ってしまいます。
一日をマイナスな感情で
過ごすか、プラスの感情で過ごすかで、物事の成否に大きな差異を生じてきます。
心を晴れやかに保ちながら、梅雨の季節を受け入れたいものです。
今日の心がけ◆天候を喜んで受け入れましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
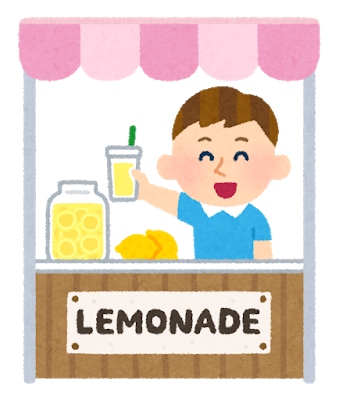
「あぁ、雨が続いて嫌だな~」と思いながら迎える梅雨ですが、そもそも何故”梅の雨”と書いて”つゆ”と呼ばれるのか、梅雨の由来について調べてみました。
中国の長江流域の地域で、梅の実が良く熟す時期に長く降る雨を”梅の雨”と書いて”ばいう”と呼ぶようになったそうです。
梅雨は、日本以外にも中国、台湾、韓国でもあるそうです。
中国では、日本に比べてとても国土面積が広いため、全土で梅雨があるわけではなく、一部の地域に存在するようです。
台湾では、なぜか年によって梅雨の時期が多少変動するそうです。
台湾の梅雨は日本同様、湿度が高く、カビが生えるなど生活に悪影響を及ぼすことが多いそうです。
韓国では、一般的に6月下旬から7月下旬が梅雨入りの時期となるそうです。
年間降水量の約30%がこの時期に集中しており、韓国での梅雨は貴重な水資源を貯める時期だそうです。
日本以外にも梅雨は存在していて、国によってはありがたい季節でもあるのだなと感じました。
ジメジメして気分が落ち込みがちになりますが、日本人として、梅雨があることを誇りに思いたいです。
そして、春夏秋冬があり、それぞれの季節の景色や旬の食べ物も楽しみたいと思いました。
保育の仕事をしていく中で、季節の制作や行事、食べ物などとても大切になりますので、学生には、今のうちから様々なことにアンテナを張って過ごして欲しいと思います。
実習指導係 林

















