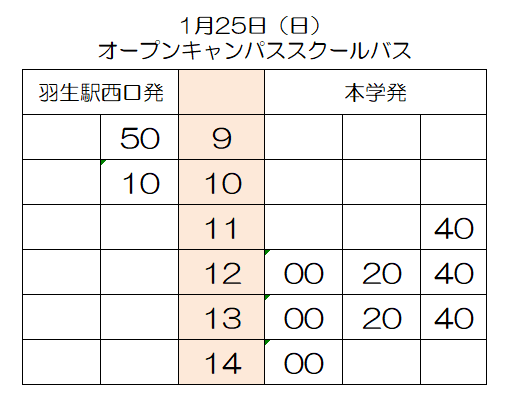今日の心がけ~職員のスピーチ~
安全のための意識
2023.01.13
厚生労働省のホームページの「職場のあんぜんサイト」にヒヤリ・ハット事例が掲載されています。
ヒヤリ・ハットとは一般に、重大な災害や事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩手前の事例の発見を指します。
例えば、直進の歩行者用交通信号が青になった時の場合です。
車をスタートさせようと思い、アクセルを踏もうとした時に、横断歩道を人が横切ったため、急いでブレーキを踏み事故を起こさずにすんだというケースです。
このヒヤリ・ハットの原因は、歩車分離式信号機は、車と人の動きを分けて表示するようになっているため、歩行者用信号機が青の時は、車両用信号機がすべて赤になることを運転手が理解していなかったことに起因します。
「知らなかった」「聞いていない」「伝え忘れた」「いつ変更したの?」が引き起こすケアレスミスを減らすために、情報の共有化をはかりましょう。
想定外の事故はいつも隣り合わせに潜んでいるとの緊張感をもちつつ、適切な対処方法についても、日頃から確認しておきたいものです。
◆今日の心がけ◆事故を防ぐ手立てを共有しましょう
(『職場の教養』:一般社団法人倫理研究所より)
交通事故は、みんながルールを知っているにも関わらず、起こってしまっています。
運転中にヒヤリハットは誰にでも経験があるはずです。
分かっていても、ちょっとの油断や慣れで起こってしまうのが事故です。
このお話のように、急な工事や何かの理由で、ルート変更やルール変更があるかもしれません。
前もって知る情報は大事ですが、スピードを出さない、かもしれない運転など、常に基本的な危険を予測していれば、回避できることもあります。
中には、自分から動いて知ろうとせず、何か起きた時に、知らなかったとか、誰かが勝手にやってるからだ等と、自分を正当化するために「知らなかった」を乱用する人も居ます。
ですが、職場では、勝手に自分だけが知って業務をしている人は居ないはずです。
上司が知っていたり、業務の繋がっている部署がしていたりします。
知らなかったを乱用している人は、自分が知らないことに気付いているのだから、知ろうとすればいいはずです。
そんな中でも、本当にみんなが知っておかなければ危険やミスが起こるかもしれない、問題になるかもしれないことについては、担当者が周知することは勿論大切です。
ですが、日々一緒に働いている人同士であれば、誰がどんな業務で何をしているかということは、全然知らないということはありません。
関心を持って見て、なんとなくでも情報は耳にしたりしているはずです。
自分の業務ではないから知らない!と言うのではなく、周りからも耳や目を使い、これはこうした方が良いのでは?とか、あれは危険かもしれないとか、納期や業務の進め方についてのアドバイスなどの情報提供や意見も大切なのではないかと思います。
全国で問題になっている交通事故などのように、みんなで関心を持つことで、危険やミスが減らせるように、職場でも、それぞれに関心を持ち、情報提供や案を出し合えるようにすることが大切だと思いました。
このお話を読んで、改めて、社会や職場内にもう少し関心を持って、見て、聞いて、共有しながら日々の業務を行っていこうと思いました。
庶務係 大澤

そのとおりですね。
ヒヤリ・ハットは多くの職場で掲げられています。
何気ない日常の行動や慣れから危険を誘発しますからね。
ここにある「知らなかった」「聞いていない」「伝え忘れた」「いつ変更したの?」や「見ていない」などはコミュニケーションの問題かもしれません。
多くの職場では多くの人々が野球やサッカー・ラグビーなどチームスポーツと同じように連携で活動をしています。
試合前の打ち合わせと同じように朝礼や会議で共通に理解するとともに、その状況変化に応じて「報告・連絡・相談」でミスをなくすようにしています。
ここではいかにこのコミュニケーションを密にかつ円滑に行われているかが重要です。
そのセクション内に情報を留めないで職場全体で共有しておけばミスはかなり防ぐことができます。
お互いに「一言多く」を基本にしていけばよいのです。
と同時に、周囲に関心を持つことも重要です。
同僚とは「同じ釜のの飯を食う」人であり、Company (パンを共にする)人です。
「隣は何をする人ぞ」ではチームとしての力は発揮できませんし、危険回避もできなくなります。
お互いに助け合う気持ちを持つためにも周囲を気にする余裕も持たなければなりません。
本学の学生は信頼される保育者を目指しています。
そのサポート役の我々教職員自らがこのようなことを守って連携して育てていきましょう。
藤田