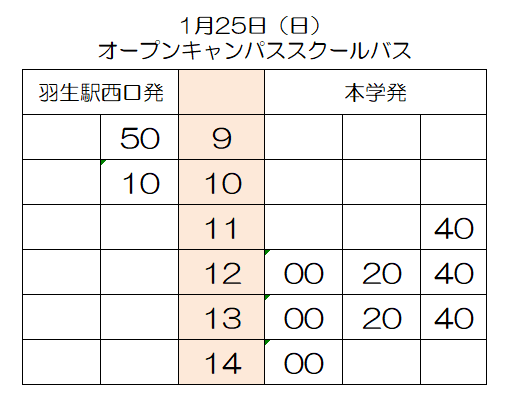今日の心がけ~職員のスピーチ~
「見て学ぶ」
2023.02.27
講演会や各種イベントを企画運営する会社に勤めているAさん。
大勢の人の前でも平然と話が出来るようになりたいと常々考えていました。
ある日、Aさんは講演会で進行を担当する先輩の補佐をすることになりました。
先輩の話し方や限られた時間で準備をする姿勢から学ぼうと考えていました。
社内では若手の先輩でしたが、その動き方は淀みなく、講演会を進めるために何をすればいいのか、全て熟知しているようでした。
Aさんは先輩の姿に、さすがだと思わずにはいられませんでした。
また、いずれは自分も先輩のような動きが出来るようになりたいと感じました。
後日、別のイベントで先輩と仕事をした際、Aさんは進行を任されました。
うまくできるかと不安に感じながらも、以前に先輩が行っていた進行を思い出し、明るく大きな声を意識することで、無事に全うできたのです。
「学ぶ」とは真似をすることから始まります。
自分自身を磨くためにも、模範となる人の良い所を見て、能力を高めたいものです。
今日の心がけ♦真似をすることから始めましょう
これを読みまして、学ぶとは真似をすることからと思っても泳げないのにいきなり海に飛び込んだりするのは無謀な事です。
では何からと思い、コミニケーションが大事、そしてそれはコミニティー趣味のサークル始めてみるのはと思いました。
自分自身、具体的に年末お正月のフラワーアレンジメントの講習に何もわからずに参加して「決まりはありません。お手本を参考に」
自由にとの事。
「えーっ」と思いましたが、これがとても楽しく真似をすることプラス自分の応用で素敵な作品が出来ました。
自分のコミニティーを探し楽しい時間を過ごし、そして真似をすることから始めてみるのは、とても良いことと思いました。
食堂 水村

そうですね。
全ては「学び」からです。
「学び ⇚ まねび ⇚ まねる」と真似をすることから学びに至ります。
漢字の字源でも「学」は子どもが、建物の中で、両手を交差して踊りを学ぶことからです。
風姿花伝にも「いよいよ物まねをもすぐにしさだめ、名を得たらん人にことをこまかに問ひて、稽古をいやましにすべし。」と。
素晴らしい人を真似をし、その学びを自分の中に取り込んでいくためには繰り返しが重要です。
昨日TVニュースでオリンピックの新種目ブレーキンの優勝者も同じようなことを話していました。
ですから、できるだけ多くのモノを見て、聴いて、触れて、嗅いで、味わってみることが重要です。
その機会が多ければ多い程、少しずつでも真似をして学んでいくことができます。
そうです。教職員も学生から真似をされる存在になっていきましょう。
「目に見せて、耳に聞かせて、やって見せ 褒めてやらねば 人は動かじ」ですよね。
藤田